




安田女子大学文学部日本文学科書道専修。神戸大学大学院総合人間科学研究科博士後期課程修了。博士(学術)。広島県立高校教諭として勤務の後安田女子大学へ。故井上桂園先生に師事し、漢字書を中心に作品を制作。博士論文テーマは「占領期における小学校『習字』教育の存廃に関する研究」。
漢字書法・書道教育学・書道教育史
書の分野について、中国では一般に「書法」、韓国では「書芸」、そして日本では「書道」と呼んでいます。すべて同じ「書」ですが、そこはやはりお国柄、それぞれ独自の特質を持っています。
書道をより専門的に学ぼうとすると、楷書はまず初唐の三大家、行書・草書は東晋の王羲之…と、私たちの視点はまず中国に向きます。もちろん書の淵源は中国にあり、中国を学ぶことは必須です。しかし、中国の書を受容し咀嚼して仮名を生み出し、和様の表現を創造した日本の書はまた独立した存在といえます。
こうした、私たちの拠って立つ足元を確実に固めつつ、その立ち位置から中国や韓国、そして人の移動とともに欧米など異文化圏へと広がる書の文化を大きく展望していくことも大切なことと思います。

鹿児島市生。筑波大学芸術専門学群書コース卒業後、鹿児島県の中学、高校教員を経て、同大大学院修士課程芸術研究科美術専攻書分野修了。筑波大学芸術学系講師、九州女子大学講師、同准教授などを歴任。専門は書道史、漢字書法(主に篆書、隷書)。篆書が現代までどう伝承してきたかに興味をもち研究中。著書にえんぴつシリーズがあり、『えんぴつで奥の細道』は90万部のベストセラーとなった。
篆書の伝承についての研究
「篆書の伝承」についての研究は、日常使用することのない書体までも、表現素材として利用する特殊な行動の研究だと考えています。さらに日本人は文字に対しては、識字だけではよしとせず、美しいことを是とする意識がかなり濃厚です。そのような文字に対する深層心理の追求と、文字の究極の「美」への挑戦を、あきらめずにコツコツと続けていきたいと考えています。
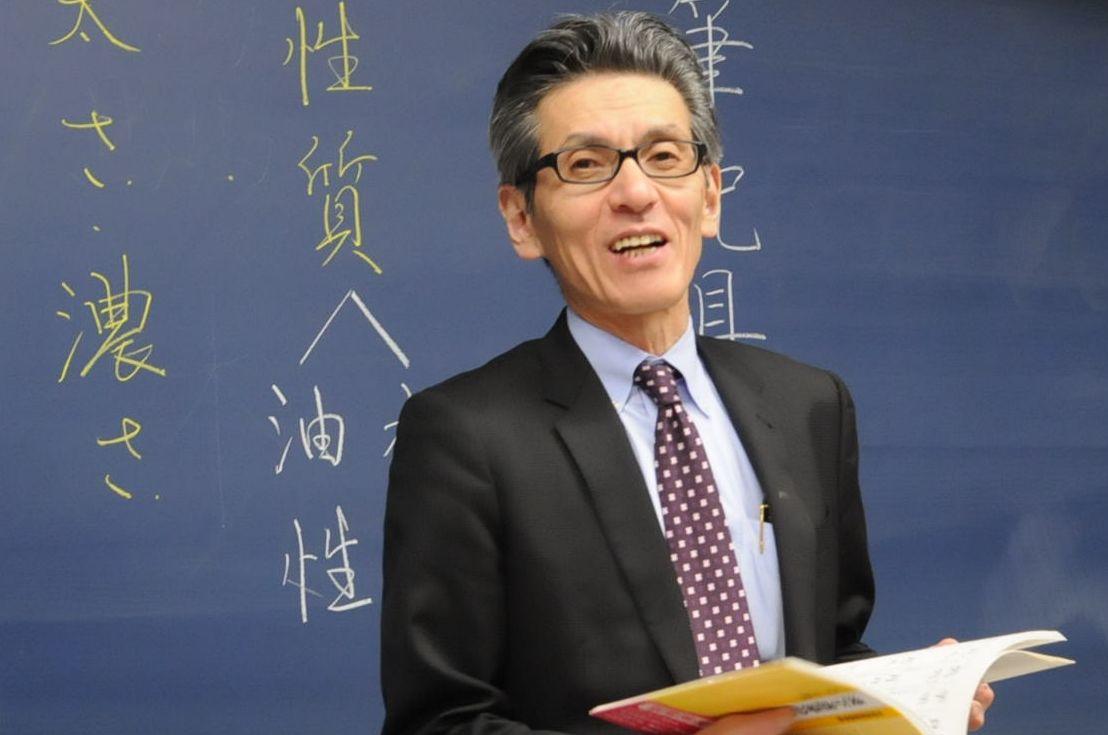
筑波大学芸術専門学群書コース卒業、同大学院芸術研究科書分野修了。県立高等学校で7年、広島大学附属中・高等学校で8年間、教諭として勤務。2003年に安田女子大学に就任。漢字作品を中心とする書作品の制作に取り組むほか、小中学校の書写と高等学校の書道授業の改善法を研究中。
漢字書法・書写書道教育学
漢字文化圏に暮らす我々にとって、文字を書くことの営みは、長い歴史と一致するほど長く、さらに、上手く書きたいという先人の自発的な意識によって受け継がれてきました。時代とともに書体書風は遷り変わりますが、優れた文字がお手本として尊ばれ、良き指導者も自然と生まれます。優れた文字とはどういうものか、文字を書くことの指導とはどうあるべきか、情報機器がさらに発達する将来においても、文字を書く限りこの思いは変わらないでしょう。書写書道に関する研究は、歴史研究、理論研究、実践研究と多岐にわたりますが、明らかになっているのはほんの一部分に過ぎません。他の学問分野に比べ、研究者が少ないのも一因になっています。

京都大学文学部卒業。同大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学。博士(文学)。中国明清時代における書文化の変容について、「法帖」の伝播という切り口から研究を行っている。著書に『明清法帖叢考』(浙江大学出版社)、『よくわかる中国史』(ミネルヴァ書房、共編著)がある。
漢字書法・中国書法史(特に法帖に関する研究)・中国明清時代文化史
私は、幼少期に習い始めた書をより深く追究するために、大学入学後より現在に至るまで、書の源流である中国の歴史や文化について研究を続けてきました。激動の中国史の中で、書という文化が一体どのようにして発展、展開、そして変容していったのか、様々な書蹟や文献史料を駆使して、その実態の解明を目指しています。また、最近では中国のみならず日本や朝鮮にまで考察対象を拡げ、相互の比較研究を試みています。

筑波大学芸術専門学群美術専攻書コース卒業、同大学院人間総合科学研究科芸術専攻書領域博士前期課程修了。筆の里工房で学芸員を務めた後、2021年に安田女子大学に着任。漢字仮名交じりの書を中心とした作品制作のほか、装飾料紙や水墨画など、様々な分野に興味を持って制作に取り組んでいる。第71回毎日書道展で毎日賞(近代詩文書)を受賞。専門は中国書法史、特に後漢時代の書体変遷史について調べている。
後漢時代の書体変遷史、漢字仮名交じりの書
近年、中国各地で活発に行われている発掘調査によって、新出土資料の発見が相次いでいます。とりわけ、後漢時代に日常通行の場で書写された簡牘などの肉筆資料は、書体の変遷の実像に迫る上で、欠かせない資料といえます。この時期の複雑な書体変遷の過程を明らかとすることを目指して、膨大な量の資料の整理、書法分析に取り組んでいます。 漢字仮名交じりの書は、現代文や詩歌などを題材として表現する、比較的新しい書のジャンルです。漢字と仮名が調和した、格調高く新鮮な表現を目指して、日々の学書に励んでいます。