




天然物化学:自然界からの宝探し
医薬品の約8割が自然界に由来するといわれ、多くの薬の元となる化合物が、植物、動物、微生物から得られています。例えば、アオカビからは抗生物質のペニシリン、巻貝のイモガイからは鎮痛薬のジコノタイド、花壇で目にするニチニチソウからは抗がん剤のビンクリスチンが発見されました。これらは自然界から「医薬品の種」を探索する天然物化学における歴史的にも重要な例です。単離された化合物は医薬品候補として有効性試験、安全性試験、臨床試験、安定性試験などの厳しい試験と評価を受け、実際に薬となるのは最初に得られた化合物の数万分の一程度ともいわれますが、それでも可能性を求めて自然からの宝物を探しています。

ストレス応答機構の遺伝子レベルでの解明と治療薬の開発
薬剤師として医療に携わるためには、その基礎として生命科学を理解することは重要です。あらゆる生物において、細胞は遺伝子に書き込まれた情報をもとに生体にとって必要な物質を作り、有害物質を除去しています。このような生命活動の仕組みを遺伝子レベルで解明することで、「健康とは何か」を深く理解することができます。例えば、酸素を使ってエネルギーを産生する生物は「酸化ストレス」に曝されており、それに対する防御機構を備えていますが、その破綻により種々な疾病に至ります。遺伝子化学分野では、生体に備わる「ストレス応答」の仕組みを究明することを目的として研究しており、疾病の予防・治療に貢献したいと考えています。
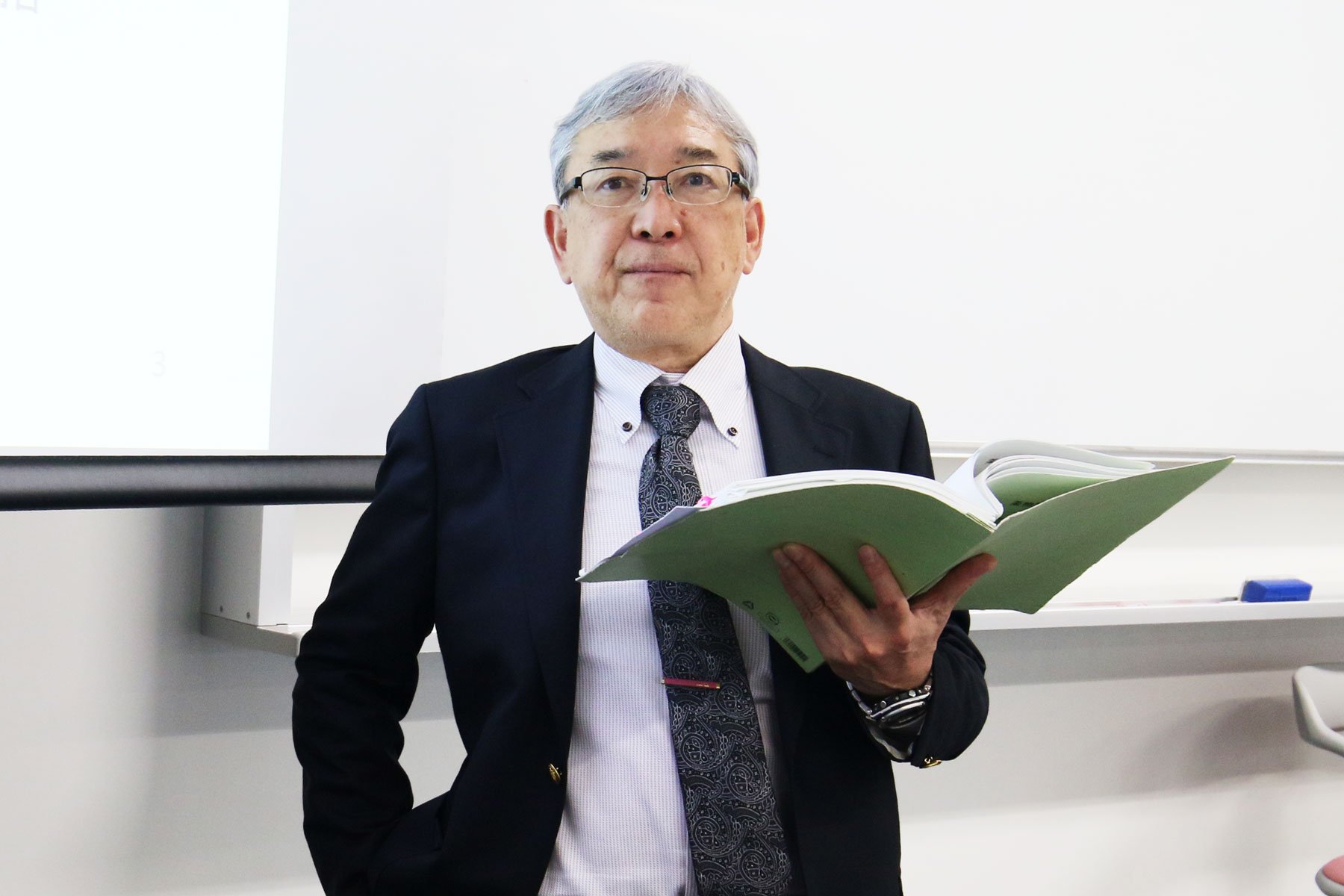
広島大学医学部総合薬学科卒業、広島大学大学院医学系研究科博士課程前期修了。広島大学病院薬剤部に勤務し、その間博士(薬学)取得。米国留学後、広島大学大学院医歯薬保健学研究科准教授・広島大学病院薬剤部副部長(兼任)を経て現職。
医薬品の適正使用、有効性・安全性評価に関する研究
大学病院勤務時には医療現場で起こる問題点を解決するための臨床研究に重点を置いた研究を行っていました。一例を挙げると、パーキンソン病治療の際、治療初期の段階から薬物の効果が十分に得られる症例と全く効果が得られない症例が存在します。その原因を明確にし、より効果的な薬物療法を提供することを目的にした研究です。個別化医療(テーラーメイド医療)の必要性を強く示唆する結果となり、患者個々に対する薬物治療に貢献できたものと考えています。現在は患者の血液サンプルを用いた臨床研究を行うには困難な環境にありますが、薬物の臨床効果に影響を及ぼす因子を国内外の文献などから検索し、より安全かつ効果的な薬物療法を構築することを目的とした “ドライな” 研究を進めています。
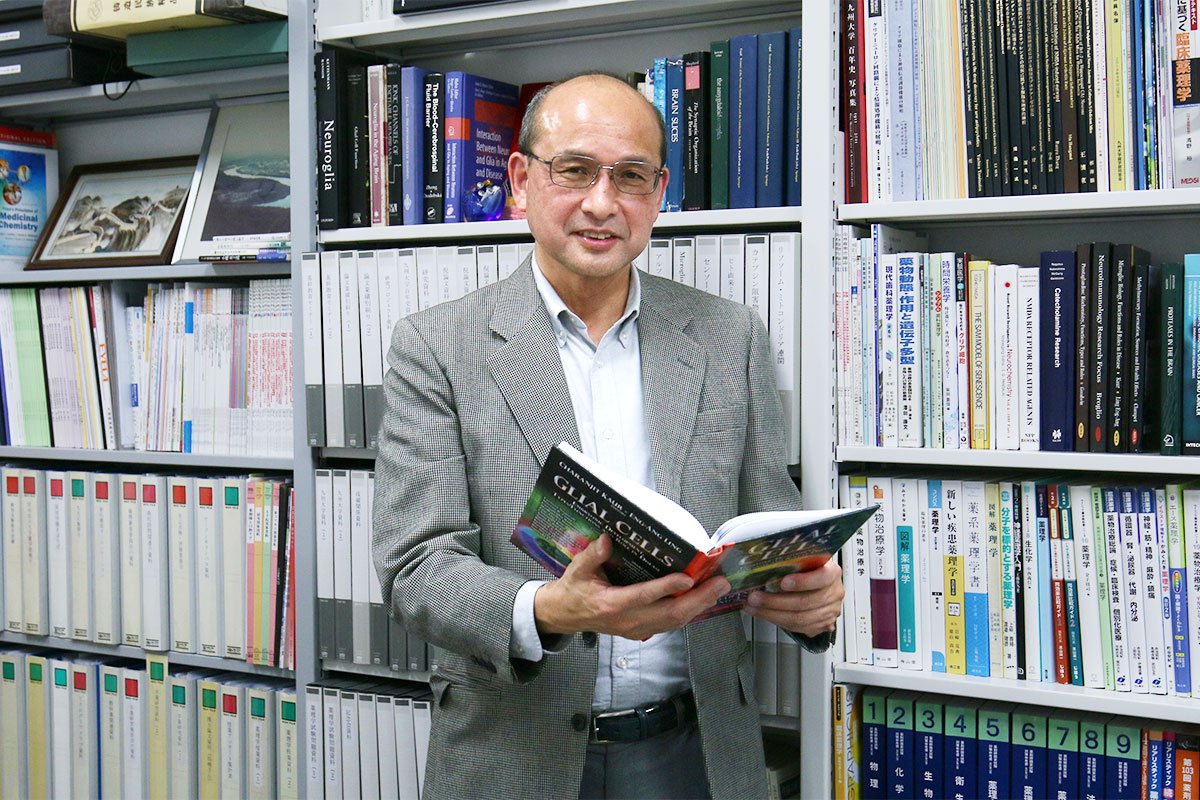
九州大学薬学部卒業、同大学薬学研究科博士課程を中退し九州大学歯学部助手、薬学博士(九州大学)。テネシー大学医療科学センター研究員、九州大学大学院歯学研究院准教授、加齢口腔科学分野(老化生物学)教授を経て、2009年より口腔機能分子科学分野(薬理学)教授。この間、副研究院長、研究院長(学部長兼任)。2018年より安田女子大学勤務。2021年より学部長補佐。現在は歯周病によるアルツハイマー病型認知症の増悪メカニズムに関する基礎研究と、口腔ケアに関する臨床研究に取り組んでいます。
慢性炎症は万病のもと、炎症はなぜ慢性化するのか?
慢性炎症は糖尿病などの生活習慣病、関節リウマチやアトピー性皮膚炎などの自己免疫疾患、ガンならびに認知症などさまざまな病気の発症・進展に関わることが分かってきています。なかなか治らず、つらい症状が続く炎症状態を慢性炎症とよんでいます。しかし、比較的早く収まる急性炎症と何が違うのか、なぜ炎症が慢性化するのか、実はよく分かっていません。炎症慢性化のメカニズムを突き止めることで、健康長寿社会の実現に貢献したいという思いがあります。現在、脳内のグリア細胞の一種で、卵黄嚢中の原始的マクロファージに由来するミクログリアに着目し、アルツハイマー型認知症の原因の一つと考えられる脳炎症慢性化のメカニズム解明に取り組んでいます。これまで、カテプシンBなど脳炎症の慢性化に関わるミクログリアの複数の分子を突き止めてきました。最近、主要な歯周病菌であるジンジバリス菌の病原因子がミクログリアを活性化して炎症反応を引き起こすことを発見し、歯周病がアルツハイマー型認知症の増悪因子になることを発信しています。
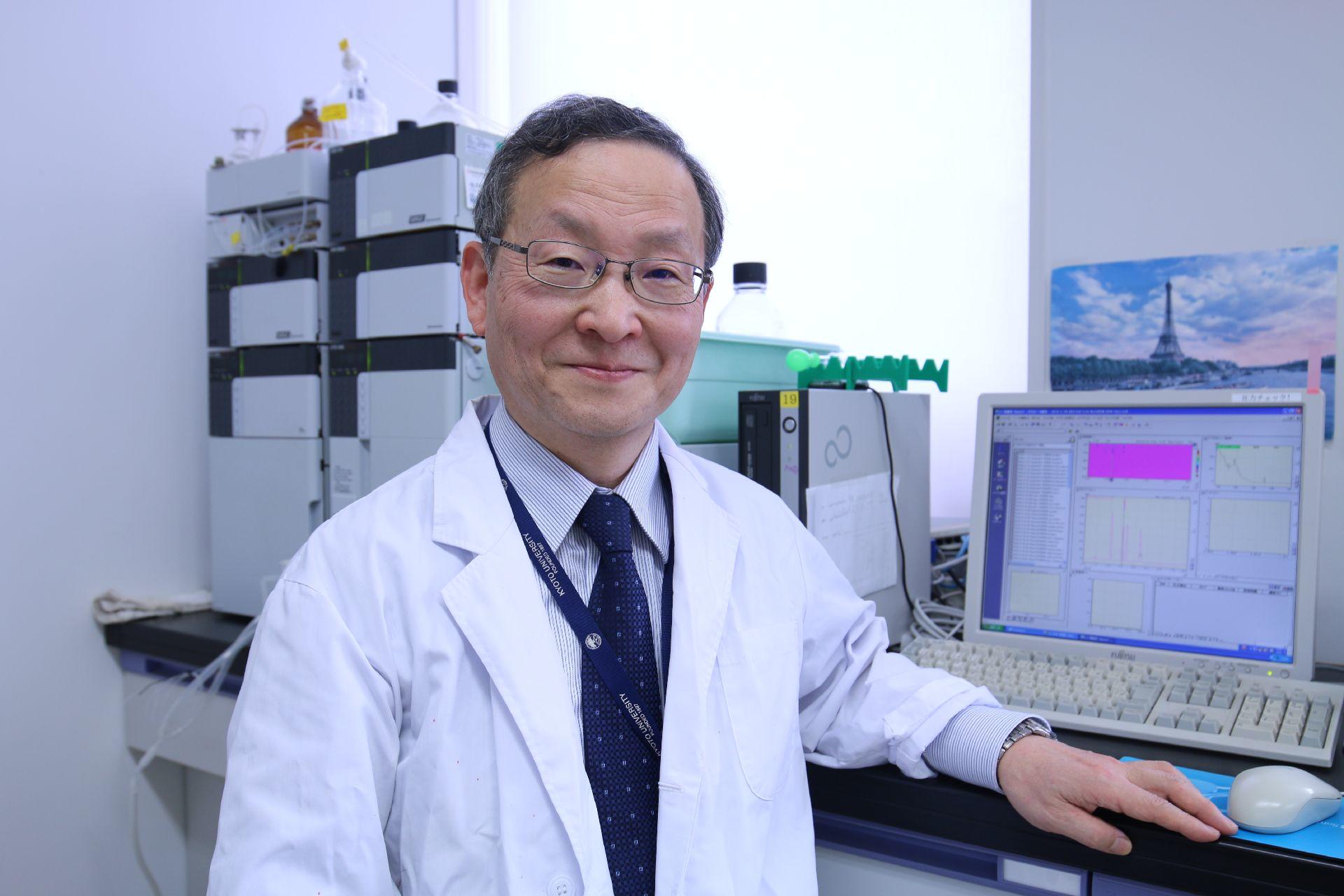
医薬品開発・医薬品の品質評価法の開発
医薬品は品質が命です。病気になった時に何の疑いもなく医薬品を用いますが、その有効性と安全性が担保されているのは、その品質が保証されているからです。それを実証・確認するのが医薬品の試験法。抗体医薬、核酸医薬など、様々な医薬品が開発されていますが、それぞれの医薬品にマッチする適切な品質評価法の開発は、その医薬品の有効性と安全性を保障する最後の砦となります。現在は、医薬品の品質評価法として汎用されている液体クロマトグラフィー(HPLC)、特に、高性能で迅速分析が可能となったコアシェル型充填剤を用いるUHPLC(ultra-HPLC)法による医薬品試験法の開発研究に取り組んでいます。

レクチンの多様な生物活性の解析-抗ウイルス薬・抗腫瘍薬の開発
毎年流行がみられるインフルエンザやノロウイルス下痢症、エボラウイルスやマーズコロナウイルスなどの新興ウイルス感染症、このようなウイルスに対する薬、すなわち抗ウイルス剤や抗がん剤の開発を目指した研究をしています。特に紅藻、藍藻や細菌より精製した糖結合タンパク質(レクチン)の生物学的性状(ウイルス感染阻止効果・腫瘍増殖抑制効果等)を解析することで、抗ウイルス剤や抗がん剤としての有用活用を目指しています。