




岡山大学工学部生物応用工学科卒業後、大学院工学研究科生物応用工学専攻を修了。1996年より島根大学、2010年より安田女子大学に在職。岡山大学在学中は、ほ乳類のイオン交換輸送体タンパク質の活性制御機構に関する研究に取り組みました。島根大学在職中より、病原細菌の感染免疫に関する研究を行ってきました。
食品関連微生物に関する研究
私の研究対象は微生物(細菌)です。ヒトと細菌とのかかわり方は多様です。例えば、病気(感染症)の原因となるものがある一方で、私たちの健康維持に役立つものまであります。特に発酵食品には色々な細菌が含まれており、健康に役立つものが多いことはよく知られています。そうした細菌の代表として乳酸菌がありますが、ラクトバチルスと呼ばれる乳酸菌だけでも250種類以上見つかっており、それらの乳酸菌の性質や役割については、分からないことがまだ数多くあります。そうした点を明らかにすることで、私たちの暮らしにもっと役立つ食品を作れたり、様々な病気の原因との関連も分かるようになることを目指して研究を行っています。
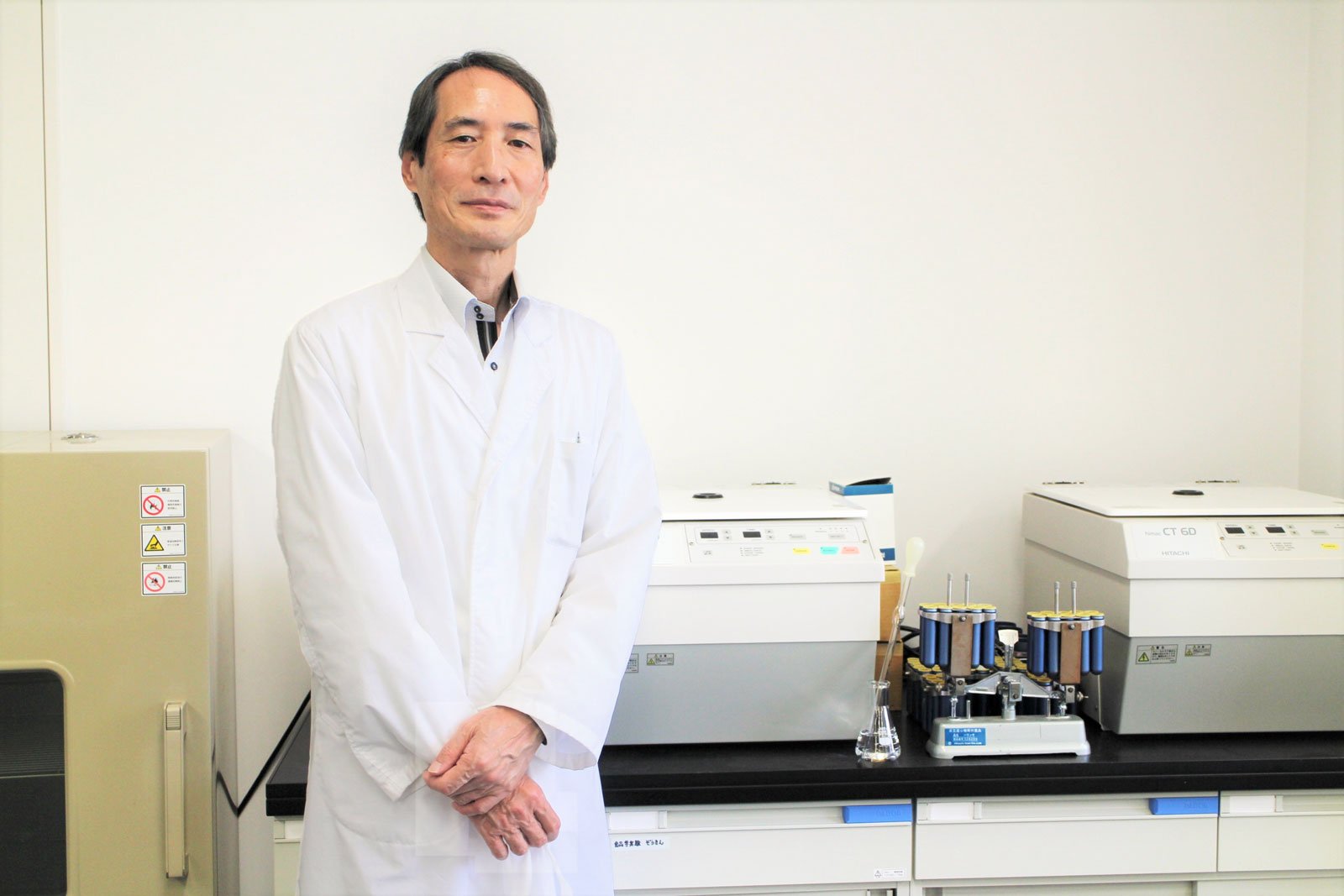
大阪大学工学部発酵工学科卒業、高知大学大学院理学研究科博士後期課程修了。博士(理学)。ニッカウヰスキー(株)などの企業で食品の商品開発を担当してきた。食品の味わいと水の関係について興味を持っている。
アルコール飲料の品質、おいしさと水に含まれる成分との関連に関する研究。
最近の研究としては、水に含まれる塩化マグネシウムなどの塩類がウォッカや焼酎などのスピリッツ類のアルコール刺激を減少させることを調べた研究、アルコール飲料の香りを嗅ぐことで得られるリラックス感は香り自体の嗜好に関連していることを調べた研究、蛍光灯下の清酒着色度増加に及ぼす要因についての研究などがある。
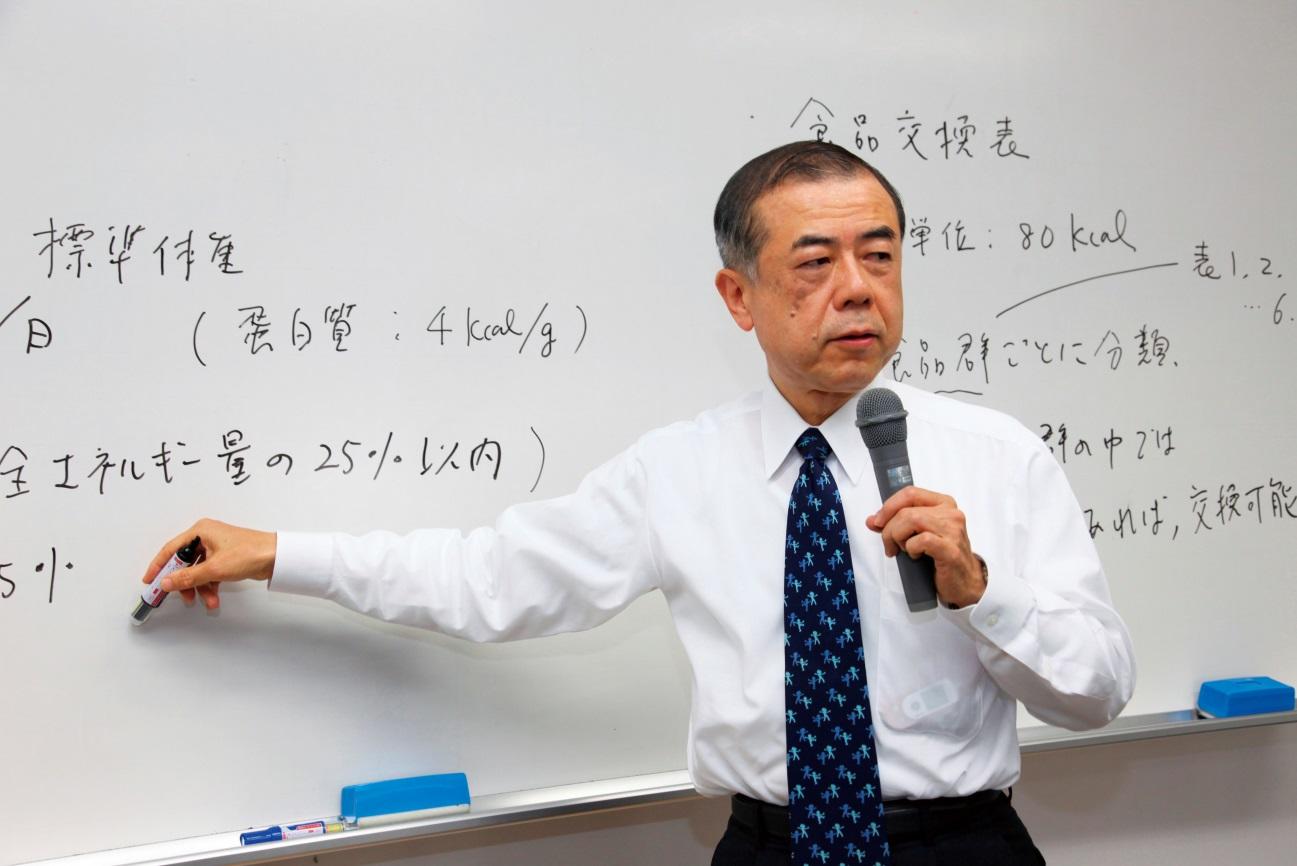
生活習慣がどのように病気の発症に関係しているのかに興味を持っています。具体的には、高尿酸血症や痛風といった病気を扱っています。広島大学医学部を卒業後、東京女子医科大学膠原病リウマチ痛風センター、放射線影響研究所で診療、研究を行い、2005年から安田女子大学に勤務しています。
管理栄養士になるために必要な病気の知識を学んでいただく授業を行います。
管理栄養士が主に取り組むのは、糖尿病やメタボリックシンドローム、骨粗しょう症といった生活習慣が関わる病気です。食事を含めた生活習慣がこれらの病気の成り立ちや悪化にどのように関係するのかを理解することによって、具体的な食事療法が自然に導き出されます。病気になるメカニズムや治療に対する考え方を学んでいただくための授業である「疾病論」、「病態栄養学」、「臨床薬理学」を担当しています。

東京農業大学農学部栄養学科管理栄養士専攻卒業。武蔵丘短期大学健康生活学科健康栄養専攻を経て2009年に本学管理栄養学科着任。
給食経営管理の分野における給食作成作業及び衛生管理についての研究
健康の保持増進のため、給食分野においても利用者の身体状況、栄養状態に応じた給食管理および給食施設に対する栄養改善上必要な指導について研究。現在の給食業務の多くは、給食提供日よりも前もって料理を作り置きして提供時に再加熱してから提供するプロセス(レディフードシステム)を取り入れているが、それに変わるシステムとして業務管理や衛生安全管理においての真空調理法の利点についても研究を行っている。

徳島大学医学部栄養学科卒業。同大学大学院栄養学研究科にて修士(栄養学)、鹿児島大学大学院連合農学研究科にて博士(農学)を取得。その後はひとの食行動に興味をもち、健康教育・栄養教育を専門とするようになる。2010年より現職。日本栄養改善学会評議員。
若年女性におけるやせ志向に関する研究
若い女性では他の年代や男性に比べてやせている人が多いです。その原因として、やせ志向の高まりや体型認識(ボディイメージ)の障害が指摘されてきました。一方、一時期は単に体重が軽いことを目指すのではなく、筋力トレーニングなどを取り入れた美ボディメイクといった考え方も広がっていましたが、最近ではその考え方も廃れてきているようです。このように若者の価値観は変化し続けており、継続的な検討が必要です。そこでアンケート調査やインタビュー調査を通して、これらの背景について検討しています。

人間の年齢や健康状態に応じた、その人にふさわしい食生活に関する研究
管理栄養学科では、初めに基礎科目として、人体の構造や食品等に関する科目を学びます。次に専門科目として人間の栄養状態を判定する方法や、病気の人の食事等、管理栄養士として必要な知識や技術などを学びます。
私の担当分野は「臨床栄養学」、「栄養管理学」などの科目です。その学習内容は、食事療法が必要な傷病者に対する食生活の在り方です。具体的には、チーム医療の一員として傷病者の傷病の状態と栄養状態に基づき、最適な栄養補給の方法や食事内容を立案・実施し評価します。改善点があれば改善を繰り返し、傷病の治療に役立つよう努める学習です。
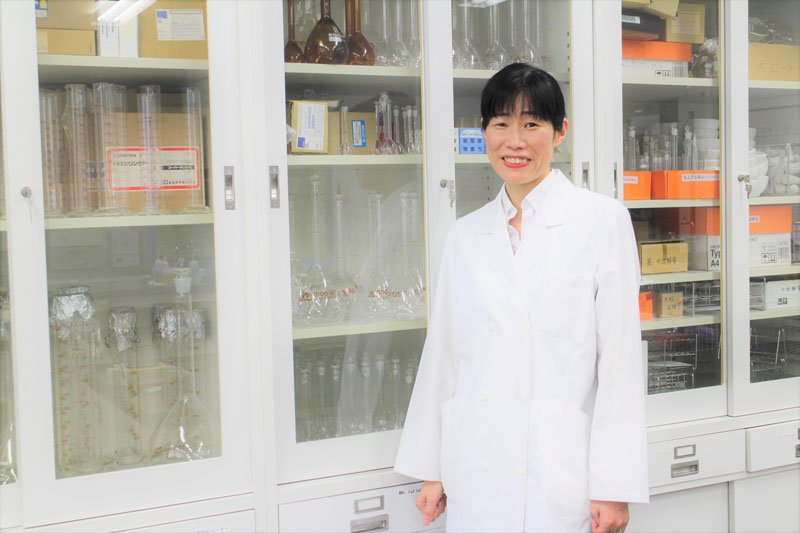
徳島大学大学院栄養学研究科博士後期課程を修了。博士(栄養学)を取得。徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部21世紀CEOプログラム研究員を経て、2005年より本学に着任。食品の機能性成分について研究を行っている。
食品の機能性成分、抗酸化作用に関する研究
野菜や果物に多く含まれる苦味、渋味、色素の成分であるポリフェノールに注目し研究を行っています。ポリフェノールには、たくさんの種類があり、人々の疾病の予防や健康の維持・増進に役立つような様々な機能があります。その中でもポリフェノールの抗酸化作用について研究しています。

神戸女子大学管理栄養士養成課程在学中に、運動生理学に興味をもち、川崎医療福祉大学大学院医療技術学研究科健康科学専攻に進学。博士(健康科学)。現在、日本体力医学会評議員、日本登山医学会代議員を務める。
女性スポーツ科学および健康教育に関する研究
女性は,月経周期によって,心拍数,血圧などの生理機能が変化します。これらの変化は,スポーツ時においても影響し,周期によってはスポーツを行う際に,生理的・心理的な負荷の増大につながります。月経周期によって起こる運動中の生理機能の変化を明らかにすることで,女性が安全にスポーツをするためのガイドライン作りにつながると考え,研究を行っています。

県立広島大学大学院総合学術研究科人間文化学専攻修士を取得。県立広島病院管理栄養士として、栄養指導や入院患者の栄養管理業務に従事。2024年より現職。日本栄養治療学会代議員。
臨床栄養学、 適切な栄養管理に関する研究
栄養は健康の維持増進や、病気の予防・治療に密接に関係しています。食べることは生きていくうえで不可欠ですが、管理栄養士は、子供から高齢者に至るまでの各年齢層や病気の状態に応じた適切な栄養管理に加えて、食べることの楽しさや大切さを教育指導することも重要な仕事としています。そのために必要となる知識や、継続して栄養管理を行う能力を習得するための「臨床栄養学」「栄養ケア・マネジメント」を担当しています。
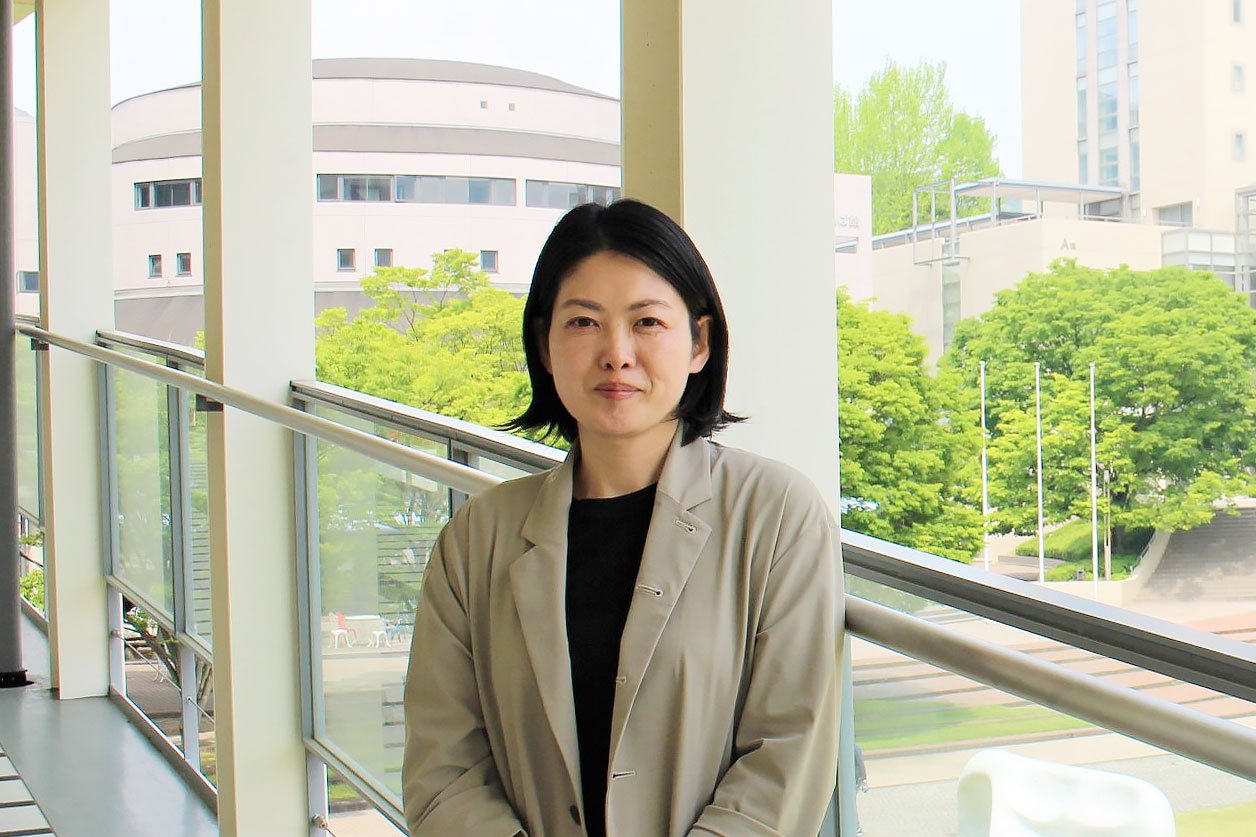
福岡女子大学大学院人間環境学研究科修士課程修了後、食品メーカーに勤務。2016年より福岡女子大学の助手を務める。2021年、福岡女子大学大学院博士後期課程修了(博士(人間環境科学))。2025年より現職。日本栄養改善学会評議員。
うま味を活用した効果的な減塩方法の検討
高血圧予防において、食塩を減らすことが大切ですが、「減塩=おいしくない」という印象は強く、積極的に取り組むひとは多くありません。 おいしさを損なわず食塩を減らす方法として「うま味」の利用が有効と言われています。うま味とは、甘味、塩味など基本味の一つです。昆布やかつお節など、だしの原料だけでなく、トマトやチーズ、きのこ、肉・魚など、様々な食品にうま味物質が含まれています。 低い濃度の食塩水にうま味を添加した際のおいしさ増強・減塩効果、またその効果への影響要因を検討することで、美味しく減塩できる効果的な方法を検討しています。

広島女子大学家政学部食物栄養学科卒業。広島県職員として、県庁・保健所(厚生環境事務所)で、健康づくり・栄養改善、食品・生活・環境衛生業務に従事したのち、現職。
公衆栄養学、食の安全に関する研究
公衆栄養学では、地域で生活している人々のよりよい健康づくりを栄養面から支援するための理論と実践を追究します。国・都道府県・市町村で取組んでいる計画・事業、多職種による地域ネットワークの構築等具体的事例に基づき研究を進めています。