




宮崎県出身。東京大学工学部航空学科を卒業後、電機メーカーで大型コンピュータを開発。その後、広島大学大学院国際協力研究科で国際協力と言語学を学び、メキシコやインドネシア等でコンピュータ教育を行った。人工知能についての研究と、コードレスプログラミングの研究を行っている。
人工知能、コードレスプログラミング
プログラミングを極力行わないでゲームを開発するための環境を研究しています。
これまでは、コンピュータ上で動くゲームを開発するのに、動作手順をプログラミングする必要があり、大変手間がかかっていました。
そこで、人工知能を使った生成AIの力を活用し、可能な限り、動作手順をプログラミングすることなくゲームを開発できる環境を作ることを目指しています。
生成AIは、文書、画像、音声を自動で生成することができます。これを利用して、ゲームに必要な要素は生成AIで作成し、人間はそれらの組み合わせを決めることでゲーム開発を容易に行うことができる環境を作ります。

広島大学工学部第二類(電気系)卒業。広島大学大学院工学研究科博士課程後期システム工学専攻修了、工学博士の学位を取得。広島大学集積化システム研究センター助教授、広島大学情報メディア教育研究センター 教授、広島大学副学長(情報担当)などを歴任。インターネットの黎明期から普及啓発活動を行うとともに、インターネットを使った動画像伝送システム、移動透過ネットワークアーキテクチャなどの研究に従事してきた。
インターネットの通信方式と運用技術に関する研究
Webページ、電子メール、SNS、チャットサービス、動画配信サービスなどは、すべてインターネットを利用するサービスとして実現されています。インターネットを構成する最も基礎的な通信方式であるInternet Protocol(IP)は、現在2種類のバージョン(IPv4とIPv6)が使用されているのですが、IPv4とIPv6は直接通信をすることができません。そのため、パソコンやスマートフォンなどは1台のデバイスがIPv4とIPv6を同時に利用できるようにしていますが、併用に必要な運用コストは決して小さくありません。この状態は既に約20年間継続しており、運用コスト削減のためには一刻も早く併用を終了し、IPv6に一本化する必要があります。本研究ではそのために必要な各種技術の研究開発を行っています。

東京工業大学(現:東京科学大学)工学部化学工学科卒業、大学院理工学研究科化学工学専攻修士および博士課程修了、英国立Leeds University化学工学専攻MSc(Eng) with Distinction。博士(工学)。東京工業大学にて助教、特任准教授、特任教授を経て、現職。エジプトで日本式工学教育を実践するためのエジプト日本科学技術大学を新設する日本-エジプト二国間プロジェクトにおいて、エネルギー資源工学専攻および環境工学専攻の設立に携わった。化学工学に流体シミュレーション、三次元印刷、数理科学、人工知能を応用する研究を行ってきた。
人工知能と数値流体力学の統合的応用による工学プロセスの最適化
人工知能(AI)と数値流体力学(CFD)を組み合わせることで、いろいろな工学プロセスをより効率的で効果的に改善することを目指しています。
CFDは液体や気体の動きをコンピュータで計算する技術で、AIは大量のデータを分析して最適な解決策を見つける技術です。これらを組み合わせることで、例えば、マスクが花粉やウイルスを防ぎつつ、呼吸がしやすいように設計できます。CFDでマスク内の空気の流れをシミュレーションし、フィルターが粒子をどう捕まえるかを分析します。そして、AIとCFDを一緒に使って最適な素材やデザインを探すことで、粒子をしっかり防ぎつつ、呼吸しやすいマスクの設計を提案することができます。この方法を使えば、いろいろな工業製品において、複数の性能を高いレベルで両立させることが可能となります。
液体や気体は私たちの身のまわりに常に存在していますので。

広島大学工学部電子工学科卒業。広島大学大学院工学研究科(システム工学専攻)修了。工学博士を取得後、国際電信電話株式会社(現在のKDDI)研究所主任研究員、大阪大学大学院基礎工学研究科准教授、広島市立大学大学院情報科学研究科教授を経て現職に。広島市立大学では、情報科学部長、情報科学研究科長を務めた。
モバイルアドホックネットワークの研究
広島市立大学では、主にモバイルアドホックネットワーク(Mobile Ad hoc Network, MANET)のルーティングやセキュリティに関する研究を推進してきた。MANETは、各携帯端末の移動により、直接に無線通信できる携帯端末が時間の経過とともに変化するので、極めて動的なネットワークである。MANETの無線通信機能を有する携帯端末を車両に置き換えることで、車両アドホックネットワーク(Vehicular Ad hoc Network, VANET)に展開できるので、MANETの技術をVANETに応用できる。また、MANETには見守りや防災などへの実用化に対する期待が大きい。実際、総務省モデル事業の一つとして、MANET を児童見守りシステムに応用した研究開発事業を広島市で2007年に実施した。
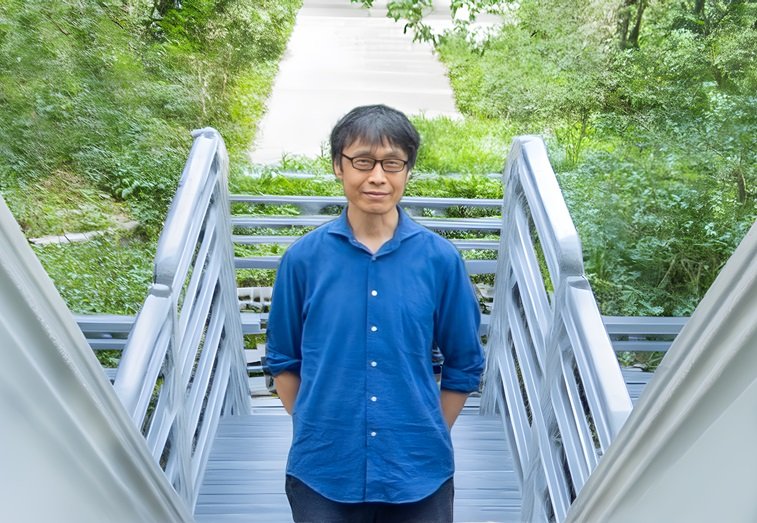
金沢大学大学院自然科学研究科博士後期課程修了、博士(工学)。金沢大学工学部助手、横浜国立大学工学部講師のち助教授、東京都市大学情報工学部教授を経て2025年4月に本学着任予定。裸眼3D表示、AR・VR、視覚情報処理の研究に従事。研究成果を社会に還元することに強い興味を持ち、さまざまな企業との共同研究で国内外の特許を多数取得し、一部はすでに商品化されています。外部リンク:https://baolab3.wordpress.com/
視覚情報の処理と表示
視覚情報の処理と表示の研究をしており、さまざまな分野に展開しています。
例えばAR・VRにおいては、脳波を用いたVR酔いの解明や視線を利用したVR酔いの軽減、ヒューマンインタフェースにおいては、VR環境下の日本語高速入力、食品の品質管理においては、マルチフラクタル解析による和牛の等級判定、スポーツや趣味においては、AIによるゴルフフォームの指導、防災においては、建築物の傾き非接触測定など。企業との共同研究である工業製品のキズ検出、科研費の研究である聴覚障害者の発音訓練、国交省の国プロの研究であるトンネル掘削作業の高度化など、社会の要請に応じた実用的な研究を進めているとともに、近年の国際学会で受賞されている3D映画館の裸眼化のためのホログラフィック光学素子を用いた3D表示、自動運転や自律移動ロボットのための車載式全方位ステレオ計測、高光効率空間浮遊裸眼3D表示などの基礎研究も進めています。

山口県出身。広島大学総合科学部総合科学科数理情報科学コースを卒業後、株式会社松下電器情報システム広島研究所(現:パナソニックアドバンストテクノロジー株式会社)で画像圧縮転送システム、携帯情報端末などの開発に従事。その後、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科で英作文自動添削システムを開発、岩国市役所を経て本学に。2008年にはコンピュータ将棋で世界ランク17位になるなどゲームプログラミングにも携わり、現在はスマホアプリやロボット開発を行う。
英作文自動添削システムの開発
Webブラウザ上で和文英訳問題が出題され、答えを入力してボタンを押すと即座にコンピュータによる添削を受けられるWebアプリケーション「サッと英作!」を開発しています。「サッと英作!」を利用した授業には、先生が黒板に赤チョークで添削する従来の授業と比べ、以下の利点があります。
・全生徒が自分の答案を添削してもらえる。
・瞬時の添削結果表示により、すぐに次の問題へと、各自のペースで進める。
「サッと英作!」は本学の授業でも使用されており、そこで得られたフィードバックを基に継続的な改良を行っています。

国際基督教大学教養学部卒業。企業就職後、東北大学大学院情報科学研究科にて修士号を取得。同博士後期課程へ進学後に単位取得退学し、岩手県立大学ソフトウェア情報学部助手。その後、東京大学大学院学際情報学府博士後期課程に入学し、単位取得退学。国際大学GLOCOM、青山学院大学HiRC、岡山理科大学、東京国際工科専門職大学(2025年3月まで)を経て同4月から安田女子大学へ。
NPO法人IGDA日本の設立理事をつとめるほか、日本初のHEVGA(全米ビデオゲーム高等教育機関連合)会員。これまで情報処理学会SSS2014最優秀論文賞,CEDEC2024招待講演など国内のゲーム開発者教育とゲーム研究の両輪を推進している。
ゲームジャムを通じた社会参加型デザイン、ゲームハッカー倫理
世界各地の文明には多様な遊びの文化があり、現代では最先端の情報技術はデジタルゲームを通じて世界を変えようとしています。ではゲームの可能性をさらに広げてよりよい社会を実現するには、どうすればよいでしょうか。まず現代のゲーム開発を理解し、なぜゲームで人の心を動かすことができるのかを理解し、プレイヤーやオーディエンスそして社会に与える変化についての知見を得ることも必要です。
ただしゲーム開発が長期化したり開発者が孤立するとゲームについての知見を共有し深めることは難しくなります。そこでゲーム開発を高速にまわす「ゲームジャム」を国内各地で開催しプロも学生も参加するコミュニティの形成を支援してきました。いよいよ誰もがどんな場所でもゲーム開発者になれる時代が近づいてきたことで、よりよい社会をつくるためのゲーム文化の発展に貢献したいと考えています。