




ビジネス社会で必要な経済・金融の知識を学び、実践力を高める
経済学では、現実に起こっている経済問題を理解できるようになるために、経済の見方を習得し、経済メカニズムの根本原理を学びます。また、観光経済学では、経済学の手法を用いて観光を分析していきます。経済の血液とも言われる金融に関する授業では、金融の仕組みや金融商品について学ぶことにより、金融が経済の中で果たす役割について理解します。応用編では、投資シミュレーションも行いながら、資産運用に関する知識も深めます。

京都大学卒業後、キャセイパシフィック航空会社で30年間旅客営業として勤務しました。その間、2年間広島営業所で中四国の営業を担当したこともあります。在職中に大阪経済大学大学院にてMBA取得後、大学教員になりました。
航空ビジネスとホスピタリティを中心に、観光全体を考える。
観光の世界にとどまらず、現代の社会、経済において航空機の役割はますます重要になっています。LCCの台頭など、航空産業自体も大きくかわりつつあると言えるでしょう。また、ハードやシステムの部分と同様に、心の問題、すなわちホスピタリティも観光を推進するうえで欠かすことはできません。授業ではこれらを学ぶことにより、観光全体、社会全体を考えていきます。

上智大学でブラジル経済・ポルトガル語を学んだ後、銀行に勤務し、3年間米国にも駐在しました。米国ジョージタウン経営大学院留学の後、総合流通業で欧米企業との合弁事業の経営や、アジア事業の管理、財務、広報、環境・社会貢献活動などを経験しました。サービスビジネスの経営モデルや国際化を研究しています。
サービス学・国際マーケティング・流通業の国際化の研究
実際のビジネスはどのように展開されているのか、を様々な角度から学んで行きます。「キャリア形成論」では、社会人になるための準備、学生生活で努力するべき方向性を1年時に学びます。2・3年時に学習するサービスビジネス論・サービスマーケティングでは、マーケティングのフレームワークを実際の企業の事例に適用させながら、ビジネスのダイナミズムを学んで行きます。身近なビジネスを支える仕組み、儲けの秘密を考えて行きます。

I am an economist with experience giving policy advice for regional development. Holding a PhD in tourism, I have more than 50 scientific publications, cited more than 1,000 times. I like travelling to know other places and cultures and I visited more than 30 countries, including the participation in almost 60 academic events. I am a co-chair of the cluster on Tourism of NECTAR (an European research network) and I serve at the editorial board of several academic publications.
Hospitality, tourism, digital technologies and sustainability
Our societies are permanently changing, opening new opportunities and also revealing new problems that need to be solved. Today, traveling and enjoying unique and authentic experiences are important elements for personal development. The internet and mobile technologies opened new ways of creating and enjoying tourism services, making travel easier and more fruitful. However, climate change and other global problems like pandemics call our attention for the importance of sustainable development.

小学生のころから小説家井上靖の大ファン。そのまま彼が学んだ九州大学へ進学しました。大学院で文化人類学を学んでいた頃、何と彼の代表作『敦煌』や『楼蘭』の舞台になった西域(今の中国新疆ウイグル自治区)の大学と九大がシルクロード合同調査団を結成。そこに飛び込んで現地の新疆師範大学にも留学、現地の方たちと交流を重ねてきました。それから約30年、ずっとこの地域の文化の調査研究に取り組んでいます。
「世界の成り立ち」を知り、「生き方」を考える。
「比較文化論」や「世界遺産論」を担当しています。遠く離れた外国から私たちの身の回りまで、世界は違った考え、異なる生き方にあふれています。そのどれもがかけがえのないものであることを想像できるよう、授業では様々な文化の起源を目指しています。「もう存在しない」ものを見つけるために必要なのは想像力。それがこの探索でみがかれるからです。こうして「世界の成り立ち」を知り、その価値に気づくことで「寛容性」も生まれます。ちょっと大げさですが、これらの授業は「倫理学」でもあるのです。

応用言語学 (コミュニケーション学 ・文化研究 ・英語教育学) の研究。人と人のコミュニケーションの仕方を学び、グローバルな場で良好な人間関係を構築する。
コミュニケーション学では、社会で、授業でのコミュニケーション方法を考えます。たとえば、自分とまわりの人とのコミュニケーションを分析して、それをグローバルな舞台で活用できることを目指します。担当授業は、コミュニケーション学、イギリスとヨーローパの社会と文化、職業英語、リーデイング、ライテイング、リスニング、スピーキングです。
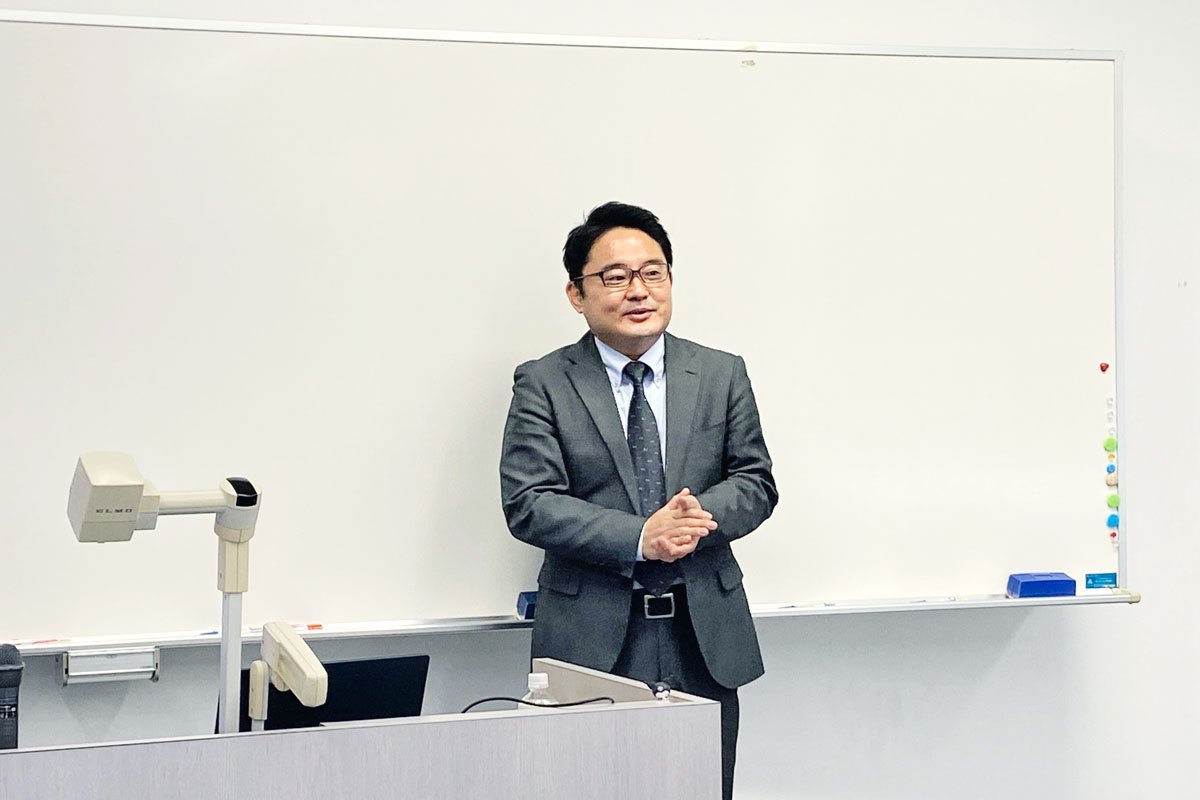
広島大学大学院工学研究科(博士課程前期)を修了後、中国地方の地域づくりを支援する民間企業への就職やイギリス留学を経て、地方シンクタンクに研究員として就職。その後、20年間、観光地域づくりをテーマに調査・研究業務に従事する傍ら、広島大学大学院で博士号を取得しました。様々な地域づくりのボランティア活動にも関わっています。
観光による地域振興に取り組む地域を支援
人口減少・高齢化の進む日本の各地では、主幹産業の衰退等による地域経済の衰退、担い手の減少、現役世代の負担増等、社会・経済が大きく変化してきています。このような地域を支える産業として期待されているのが「観光」です。観光ニーズの多様化により、どのような地域でも観光による地域振興の可能性がある状況の中、多くの地域で観光による地域振興に取り組んでいます。観光調査やデータ分析だけでなく、観光による地域振興(観光地域づくり)に取り組む地域を支援するために必要な研究を進めていきたいと思っています。