




京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻修了。旧建設省道路局・旧国土庁計画調整局・京都大学安寧の都市ユニット・宮津市役所を経て2019年4月より安田女子大学に着任。まちづくりの理論研究と行政での実践経験を元に教育・研究活動に取り組んでいる。
まちづくり論、公共政策、交通工学、土木計画学
公共政策とまちづくりに関連する講義を担当します。公共政策とは、社会全体に影響のある課題に対して、行政機関のみならず住民や民間組織が行う公共的な政策全般を指します。その中には「まちづくり」も含まれますが、これら公共政策は全て住民の生活の質を向上させることが究極的な目的です。そうした場合、住民の生活の質とは何か、どうすれば生活の質が向上させられるのか、について考えることは公共政策の根源的課題であると考えられます。そのような本質的な問いを常に置きながら、具体的な事例を元に一般的な課題解決手法を探索していきます。
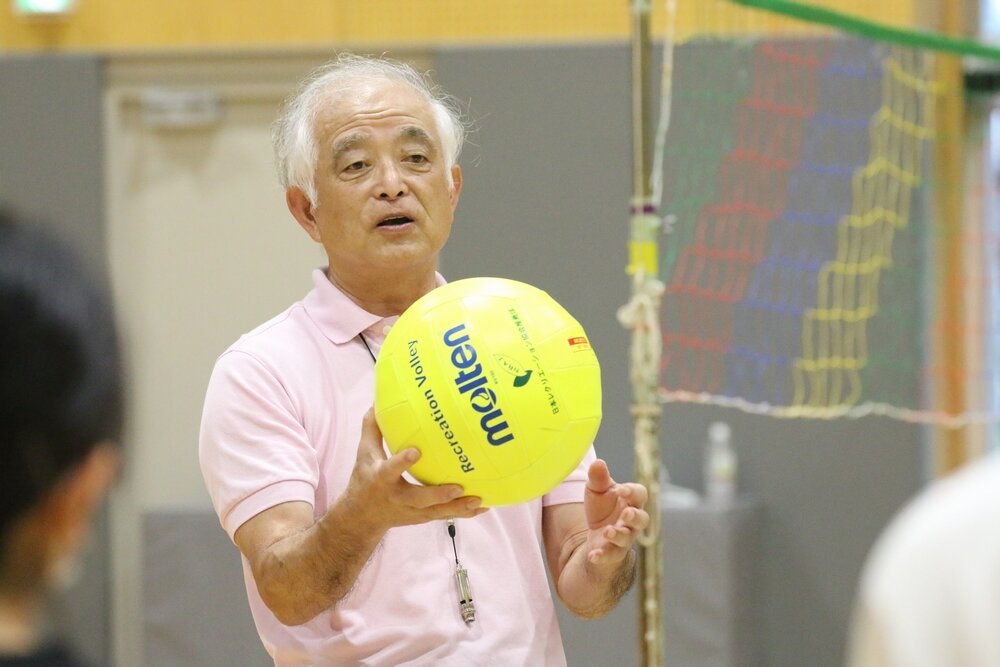
日本体育大学大学院体育学研究科体育方法学専攻修了、体育学修士。呉工業高等専門学校と近畿大学呉工学部で非常勤講師を勤め、1980年に安田女子短期大学家政科専任講師として着任。以来、健康スポーツ部門の授業を担当し、生活科学科、大学・日本文学科、人間科学科、生活デザイン学科を移籍しながら現在に至ります。近年では、授業でのボランティア活動を含めて学生と伴に、地域貢献に努力しています。
生涯スポーツ論、野外活動、ボランティア活動の実践研究
生涯スポーツを研究テーマとしています。主に「レジャー・レクリエーション」が地域活性化に貢献することを検討しています。地域活性化については、ボランティア活動やいろいろなスポーツとの関わりについて現地実態調査をしたり、プロジェクトを組んだりしています。また、視野を広げるために他ゼミ、他大学と合同ゼミのフィールドワーク等も実施しています。

東京大学法学部憲法ゼミの出身。イギリス留学中に国際平和・安全保障に関する国際関係論の研究で博士号と法廷弁護士の資格を取得し、帰国後留学経験を活かした比較法制史研究とともに、前任校では、人権教育に携わってきました。生まれ育ちは京都市です。父の出身は鳥取県西伯郡成実村(現米子市)です。日本再生は地方から。地球規模で考えて、身近な地域で行動する。モットーは、環境、伝統、自由。
基礎法学、法制史、憲法、国際関係論(英国学派)
1.主権、つまり誰がこの国の主か、その統治権は誰の意思に由来するのか。これは民法的には委任や信託の問題として捉えられますので、委任や信託の事務処理報告責任(アカウンタビリティ)を憲法に応用した制度の比較法制史的研究をしています。2. 平和のためだからといって自衛権まで否定する法理はあるのか。国際関係・国際組織の実証的研究を土台に、人権としての平和的生存権を保障する国の責任規範とは何かを比較法制史的に研究しています。3.基本的人権の尊重の原点に遡り、市民的自由と法の適正過程の法制史研究を進めています。

京都大学法学部卒業後、住友金属工業(株)勤務、京都大学大学院、京都大学助手、広島大学助教授、同教授、同名誉教授を経て、2023年9月に本学に着任しました。労働法(ワークルール)をあらゆる分野にわたって研究しています。弁護士登録も行っています(広島弁護士会所属)。理論と実務の架橋にも力を入れています。
労働契約法と労働団体法の基礎理論、フランス労働契約理論、労働法の現代的課題
若いころはフランス労働契約理論を歴史的経緯も踏まえつつ体系的に研究していました。これは『フランス労働契約理論の研究』という著書に結実しました。その後、わが国の問題にも視野を広げ労働契約法と労働団体法の基礎理論の研究に打ち込んできました。前者は『現代雇用社会と労働契約法』という著書に結実しました。それと並行して、変化の激しい雇用社会を見据えてデジタル給与払いなど労働法の新たな問題についても意欲的に研究を進めています。また、弁護士に対する労働法教育や学生・一般に対するワークルール教育にも力を入れ、そのためのテキストである『ワークルールの基礎』を執筆しました。

広島大学経済学部卒・同大学在学中より、秀和システムトレーディングをはじめとした出版各社にてテクニカルライターとして書籍や連載記事の執筆活動に従事する。福山通運事務職を経て、広島大学経済学部助手に就任。同大学社会科学研究科マネジメント専攻修了後、2002年に安田女子短期大学着任、2005年に安田女子大学に転籍。
情報学、経営学、経営マネジメント、知的財産、交通経済学
統計を元にしたデータサイエンスに関する科目を担当しています。データサイエンス分野においては、PythonやRなどのプログラミング言語を用いた解析を行うこともありますが、プログラミングが主となり、肝心のデータ処理が不十分なままに終わることも珍しくありません。そのため、Excelを用いることで、理解しやすく、さらには社会においても即戦力となれることを目的にしています。
また、複数の分野が関係した学際領域の指導経験が長く、起業による地域創生や、交通を主とした地域振興にも関わっています。
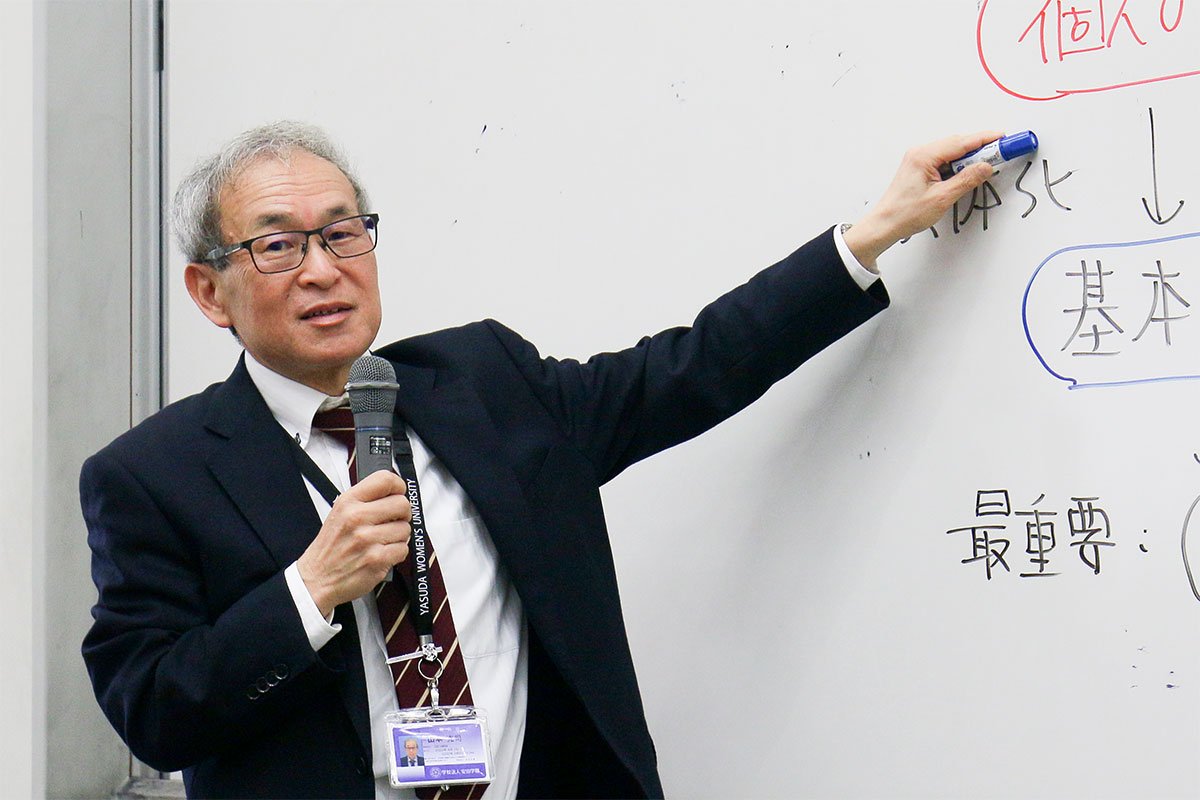
明治大学法学部・早稲田大学大学院法学研究科を通して法学を専攻。早稲田大学社会科学部・佛教大学大学院社会福祉学研究科を通して社会保障・社会福祉学を専攻。法学と社会福祉学の学際領域である権利擁護が専門分野。特に、認知症高齢者の人権・権利擁護を研究。博士(社会福祉学)。社会福祉士。2022年4月着任。
憲法学(人権論)、権利擁護、認知症高齢者の人権保障・権利擁護、高齢者法学
法学系科目と社会福祉系科目を担当します。法学系科目では、憲法、行政法、地方自治法、刑法という国家と国民の関係を規律する「公法」といわれる分野の法を担当します。なかでも憲法は、私たちの基本的人権の保障を目的とする国家の最高法規です。私たちの個人の尊厳を実現するために重要な役割を果たしています。憲法の授業を通して基本的人権について、理論的に役割、種類、内容などを学習し、高い人権意識を形成します。人権の知識は、様々な法律を学習するうえで不可欠です。また、憲法の生存権の理解は、社会保障制度を理解するうえで不可欠です。社会保障論の講義では、生存権を具体化する制度を学び、共生社会の実現を考察します。

同志社大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程にて「日本政治史」を専攻。長州生まれですが、上洛して約30年、經世濟民の學を修めるとともに蘭學の修業もしました。2006年、大村益次郎研究で阿南・高橋賞受賞(軍事史学会)。2008年、博士(政治学)。同志社大学法学部助教等を経て、2020年4月より現職。
日本政治史、明治維新史、政治学
政治学関連科目を中心に担当します。私の専門は日本政治史という分野です。これは権力関係を中心に見た日本の近代史です。あらゆる出来事の記録はそのままでは「歴史」にはなりえず、歴史叙述とは出来事相互間の脈絡を求める営みともいえます。そして、歴史について学び、そこから何らかの教訓を導き出そうとするならば、その時々で真剣に生きた先人に対する謙虚かつ冷静な態度がなくてはならないと考えます。私は自身の研究においても、「当時の人はなぜその道を選んだのか」という「問い」を重視しています。同時代的視点に立って初めて歴史が生きたものになると考えているからです。

北海道教育大学大学院教育学研究科学校臨床心理専攻修了(教育学修士)。札幌市内の公立中学校で国語科教諭として10年間勤務。生徒指導・教育相談・進路指導を担当。北海道教育大学教育実践総合センター教育臨床相談室共同研究員、同大非常勤講師、広島修道大学学習アドバイザーを経て、2016年4月より安田女子大学に着任。公認心理師。
国語教育学、心理教育、学習支援、ピア・サポート
日本語文章表現・口頭表現を担当します。労働人口の減少に伴い、AI(人工知能)やRPA(事業プロセス自動化技術)による定型業務の自動化・効率化が進められています。こうした情報技術の進歩によって、仕事だけでなく私たちの生活も格段に便利になってきています。しかし、人の複雑な感情を察知し理解し合うこと。比較・検討をしながら「最適解」ではなく「納得解」を生み出していくこと。それらは、私たち人間にしかできない特別な能力です。グループ・ディスカッションやプレゼンテーション、小論文指導を通して、論理的かつ批判的思考力を鍛えるとともに、豊かで美しく繊細な日本語を実用的場面で使える力を伸ばしていきます。

韓国外国語大学東洋語学部卒業・同大学国際地域大学院日本学科政治専攻修了後、文部科学省国費留学生として2015年に渡日。京都大学大学院法学研究科法政理論専攻修了(法学博士)。同大学の特定研究員・助教等を経て2025年4月より安田女子大学着任。
政治学、行政学、公共政策
行政学に関連する科目を担当しています。行政は、私たちの社会に不可欠な存在です。日頃のごみ収集や道路の整備、保育施設の運営といった目に見えるところだけでなく、災害への備えや福祉制度の設計、財政運営など、普段は意識しにくいところにも、行政は深く関与しています。授業では、理論と事例の両方に注目しながら、行政の役割と仕組みについて、幅広く考察していきます。