



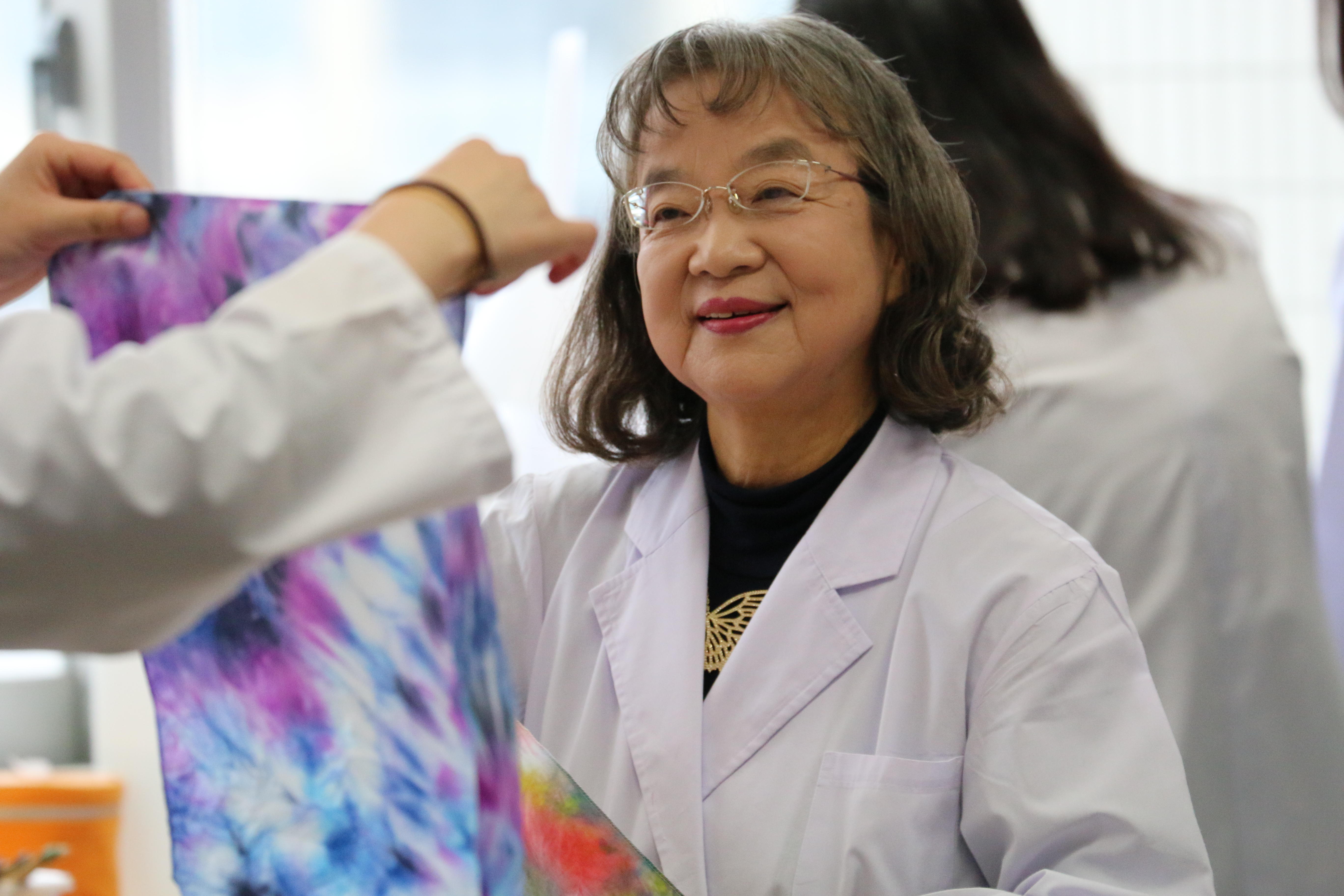
家政学・衣環境学分野における研究。主な研究課題は、寝具及び冷え症。
人間―衣服―環境系における衣の分野を主要課題としています。衣服は私たちの体を守り、心を表現する最も身近な友人です。どのような衣服を着用すれば、健康で快適で楽しい生活が送れるのか、科学的なデータを基に検討しています。ここでの健康は、WHOの健康の定義に沿った内容を意味しています。すなわち、肉体的(体温調節の補助など)・精神的(ファッションなど)・社会的(TPOなど)側面を重視した内容です。昼間の衣服はもちろん、夜間の衣服、すなわち寝巻や寝具についても研究しています。
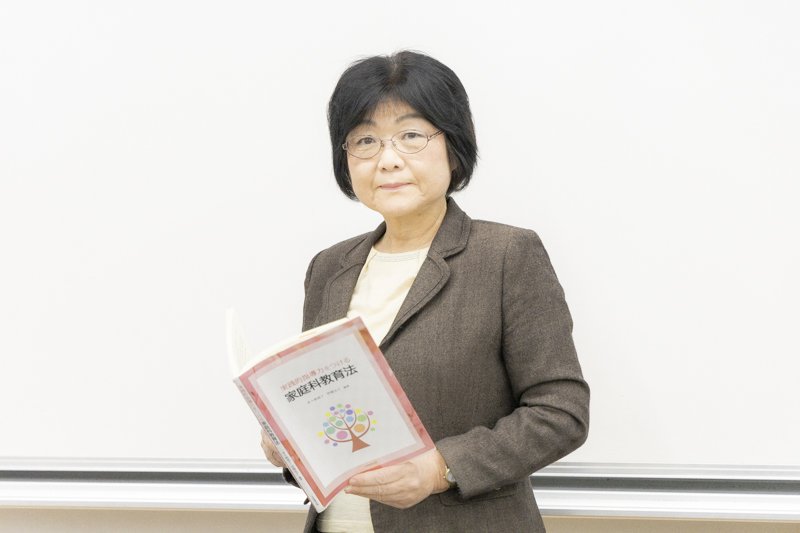
広島大学大学院教育学研究科教科教育学専攻修了、博士(教育学)。広島大学学校教育学部、広島大学大学院人間社会科学研究科を経て2024年4月より安田女子大学に着任。専門は家庭科教育学(日本家庭科教育学会賞 受賞)。主な著書『実践的指導力をつける家庭科教育法』(大学教育出版)、『「気になる子ども」と共に学ぶ家庭科』(開隆堂)等。
家庭科教師として家庭科の授業を実践してみよう
これまで学んだ家庭科で最も楽しかった授業はどのようだったでしょうか。その授業はなぜ楽しかったのでしょうか。楽しい中にも「なぜ?」「どうして?」「知らなかった。もっと知りたい」という探求心が生じたのではないでしょうか。家庭科教師は授業を行うにあたって、いろいろな工夫をしています。子どもの生活実態を踏まえて、どのような教材を用い、どのような教育方法で授業を実践すればよいのかを、大学では『家庭科教育法』などの授業科目で具体的に学びます。その履修を通して、子ども達の生活に寄り添い、家庭科で学んだことが子ども自身の生活に還元されるような家庭科授業を実践できる家庭科教師になってほしいと思っています。

京都大学大学院工学研究科環境地球工学専攻修了、博士(工学)。大阪市立大学都市研究プラザ、京都大学大学院医学研究科安寧の都市ユニット、山口大学大学院創成科学研究科を経て2024年度より現職着任。専門は建築計画、医療・福祉施設計画、地域計画。
日常生活行為から生活空間を考察する
一度建設した建築や都市空間は気に入らないからと簡単に取り壊し新しく作ることは大富豪でもなければ非常に難しいです。そのため一度建設されてしまえば不都合があっても騙し騙し耐用年数が来るまで使い続けることになります。30~50年という時間が経過すれば人は老いるし、新たな命も誕生します。時間経過に耐え得る空間を考えるためには、人々の生活行為を丁寧に観察し行動原理を解釈する必要があります。人の日常生活行為に基づく、空間の使い方、空間の計画の仕方を研究しています。

スポーツ科学(スポーツにおける巧みさの獲得と指導に関する研究)
講義科目(からだの科学、運動生理学など)では、女性の心身の特性を踏まえたスポーツ・トレーニングの理論、およびそれにもとづく具体的方法を紹介しています。実技科目(健康スポーツ)では、身体運動を通じて事物の本質的理解(肌で分かる・体感する)のための基礎技術を修得させ、生涯教育としての心身の健康教育・運動習慣の基礎作りを行っています。

広島大学工学部卒業後、サントリー株式会社にてビールの醸造技術開発に携わる。出産・育児期間ののち、独立行政法人酒類総合研究所、アンデルセングループなどを経て、2016年より現職。2007年、広島大学において博士(農学)を取得。
食生活論、調理学など(食情報が生活に与える影響の研究)
インターネットの発展に伴い、様々な食や健康に関する情報があふれています。よりよく生きるためには、多くの情報から自分に必要な情報を適切に選びとり、実践する力を身につけることが求められます。食に関する基本的な知識から、実践するための調理技術まで幅広く学べます。食と健康に関する情報が私たちの生活に与える影響について、消費者、事業者など多角的な視点から、計量テキスト分析の手法を用いて研究しています。

文化学園大学大学院生活環境学研究科被服環境学専攻修了。博士(被服環境学)。渡仏し、Université Catholique de l'Ouest , Angersで仏語を学び、Parisのドメスティックブランドでパターンメーキングや縫製の実地研修を受ける。帰国後、ANNE KLEINやato.などのデザイナーズブランドでパタンナーを勤める。2018年より現職。
被服学・被服構成学 “縫うことですべてがわかる”
「アパレル業界のすべての職種の人が縫えなければ、仕事が成り立たない」と教えられ、以後、“縫うことですべてがわかる“を信条として教えています。近年は、デジタル化の流れを受け、3D-CADを使用してパターンメーキングを行っていますが、縫製の基礎はしっかり身につけておく必要があります。主な研究内容は、衣服の3Dシミュレーションにおけるパターンと素材変形の関係、生成AIとファッションの親和性などです。

奈良女子大学大学院人間文化研究科生活環境学専攻後期博士課程修了、学術博士。幼少期の在外経験が契機となり多様な文化・住まい・住まい方に関心を寄せる。専門は住居学。学生時代は長期休暇を海外で過ごし、渡航した国は数多い。共著に「住まいのデザイン」朝倉書店、他。近年は広島市がより美しい街となるよう景観審議会委員として活動中。
住生活論、人間工学、住環境学、インテリアデザイン論、色彩学など
世界や日本の住居史を学び、私たち人類はどのようにして住まいを獲得してきたのか、これからの住まいがどうなるかを考察すると共に、私たち人間の住む住空間に求められる、機能的な条件・使いやすさや快適性に関する事項について解説します。この他、インテリアの諸条件・色彩計画など、適正かつ快適で美しい空間に求められる項目についても講義しています。卒業研究では景観色彩や流行色など、色彩を題材として扱う人が多くいます。
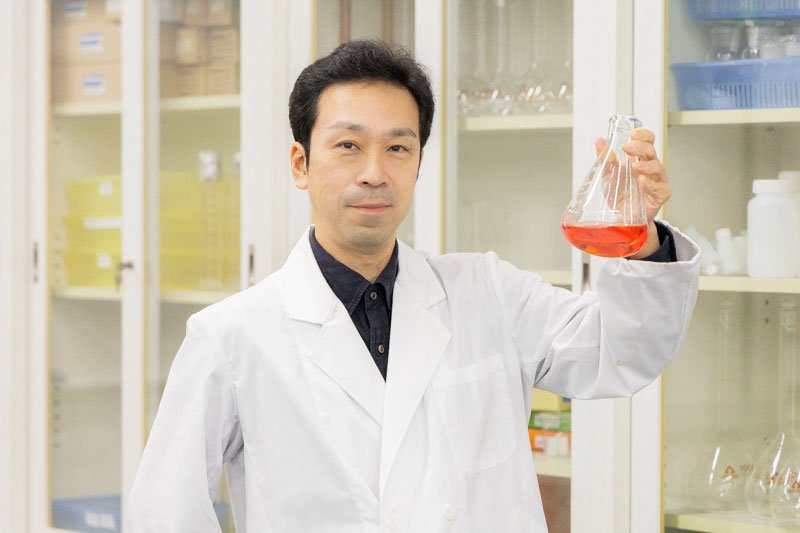
東京工業大学(現:東京科学大学)工学部第3類(化学)から、同大学院生命理工学研究科博士課程、博士(工学)取得。学位取得後、長崎大学薬学部、医学部を経て2019年より現職。インフルエンザウイルスの増殖を抑える薬の候補を、食品をはじめ・環境微生物・薬用植物等から探索。業績に特許第7061394号「キノリノン化合物および抗RNAウイルス薬」など。
「食」を化学・生物学的視点から捉える
座学では「食品学」「栄養学」「食品衛生学」、実験実習では「食品学実験」「食品加工学演習」などを担当しています。生活デザイン学科の食分野の学びでは調理ができるようになることだけではなく、食品の栄養成分などには化学的・食中毒などは微生物など、生物学的な視点が欠かせません。高校で化学や生物を十分に学んでいなくても解り、かつ実生活にも役立つような授業や実習を心がけています。

広島市立大学大学院芸術学研究科博士後期課程修了、博士(芸術学)。地域の特色を活かした芸術祭や産官学連携のアートプロジェクトおよび国内外での展覧会を中心に、現代美術、コミュニケーション・デザイン、写真研究など視覚芸術の領域を越境する活動に取り組む。2020年度より本学着任。
日常生活とデザインの関係を手で考える
「絵画・デッサン」「造形表現」など実技科目を担当しています。絵画においては日常的なサービス・商材とデザインの関係を見える化することに挑戦し、デッサンでは表現力はもとより分析的に対象を観察する方法を重視するなど、幅広く〈生活をデザインする〉ことに繋がるよう心がけています。また学芸員資格関連の授業では、何気ない嗜好を再発見する課題や家庭を彩る装飾デザインの企画を行い、実生活と地続きで取り組んでもらえる工夫をしています。