



教育講話Ⅲ 講話「わが人生の歩き方」
2023.11.20
本年度第3回の教育講話として、本学科所属の教員が語る会を開催しました。本年5月に続いて今回も2名に登壇していただき、「わが人生の歩き方」について「これまでと今、そしてこれから」について語ってもらいました。
講話を聴いた後の学生の感想文から、「人生の分岐点での決断」「信念を持って揺るぎない生き方」を聞き取り、自分の生き方を振り返り、これからの在り方を考えたことが読み取れます。「小さな選択を繰り返す中で、時に自分にとって大きな選択に出会うのが人生なんだと思う」といった学生の名言も見られます、
また、多くの学生が指導者・保育者として何が大事かに気付いています。子どもの興味を大事にする姿勢や、指導者の言葉が人生を方向付ける契機になることに頷いています。
教員・保育士を目指している学生が各々に自身のこれまでを振り返りながら、生き方やこれからの課題を考えるきっかけになったようです。「先生方から普段の授業では聞けない話を聞くことができ、学びの多い時間になりました。」(4年Sさん)の感想のように、授業以外でのこうした教員の語りが意義深いことが伺えます。【徳永隆治】
教育講話要旨(「私の来歴」)
初めに自分の略歴や専門分野(教育心理学、教育工学:新しいことがわかる・出来る・身に付くメカニズムを探究し、教授者や学習者を支援する学問分野)について簡単に紹介してから、当該分野に興味を持つに至った経緯や、研究者を志すようになったいきさつについて話した。小学校時代(1980年代)に、学習速度の異なる児童全員が参加できる授業を経験したことから教員という職業を志したこと、次に今度は大学の教職課程で「先生の先生」として、教員を目指す学生やより良い実践を目指す現職教員に「教えること・学ぶこと」についてより有意義な知見を提供する役割を務めたいと考えるようになったことを語り、いま現在の教員生活が非常に充実していること、今後もさらに教育研究活動に邁進していきたい旨を述べた。(五十嵐亮)
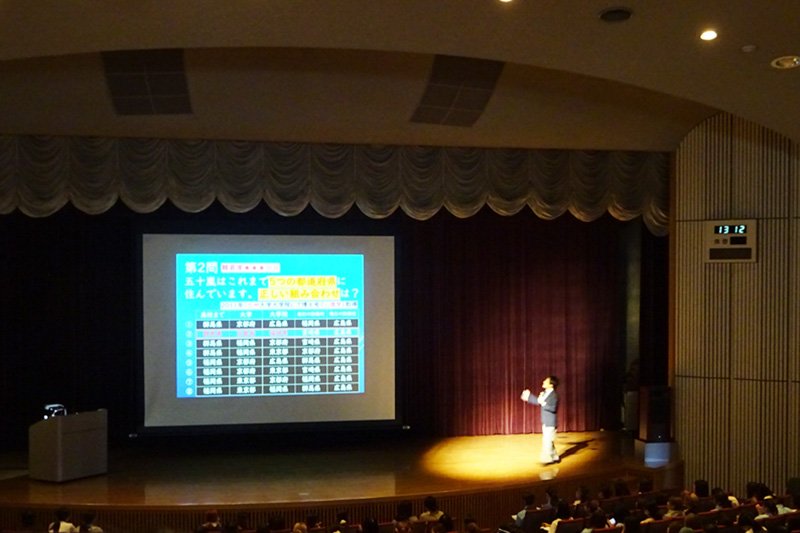
教育講話要旨(「あなたは、どこでルビコン川を渡るのか」)
今回、私に与えられた課題はこれまでの私の人生、生き様について語ることでした。人生は大小様々な選択の結果、紡ぎ出された物語です。私の最大のそして後戻りできない選択、すなわちルビコン川の岸に立ったのは、郷里千葉県の高校日本史の教職内定を辞退し、博士課程後期入試に挑む決断でした。私は、小学校の時から歴史は好きなのに社会科の授業には今ひとつすっきりできない思いでした。そんなときに出会ったのが、苦手な理科を面白いと感じさせてくれた中学校3年生の時の理科授業でした。それは当時最先端であった米国の高校向け物理教育プログラムでした。社会科でも、子供が歴史の面白さを感じられる授業ができるはずだ、そんな授業ができる教師になろうと考えました。さらに、そのような授業ができる教師を育てる大学教員に、さらにそのような大学教員を育てられる大学教員になろうと考えるようになりました。「「先生の先生」の先生」です。この夢を叶えるのは、決して簡単なことではありませんでしたが、それを支えたのが二つの座右の銘、すなわち「斧を磨いて針を作る」「水急なれど月を流さず」です。学生の皆さんも今後、自分の人生を方向付ける後戻りできない選択をしなければならないこともあるでしょう。斧を磨いて針を作り出す根気と意志の強さ、急流に流されない自分の月を持って、思い切ってルビコン川を渡っていただきたいと思います。(棚橋健治)
