



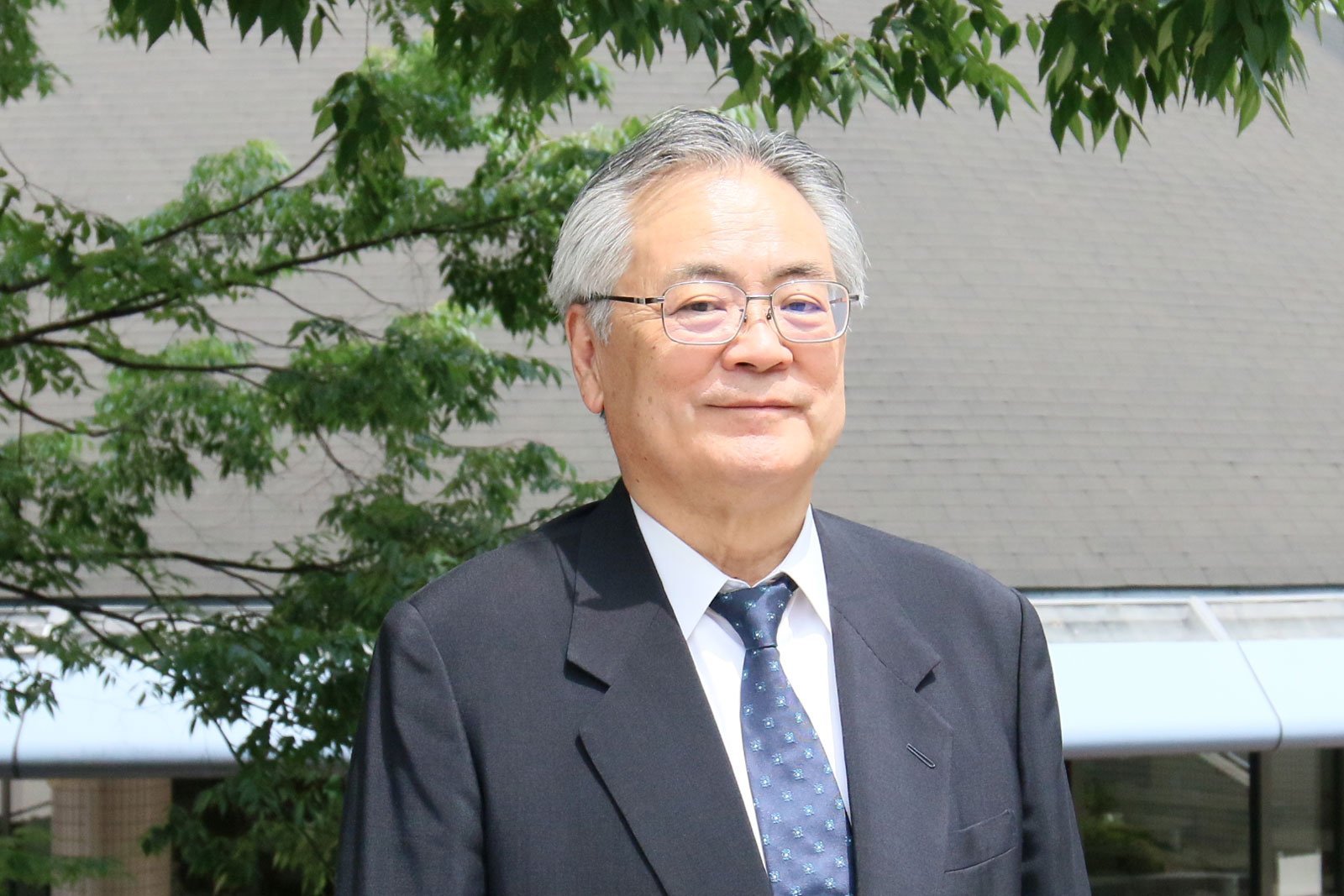
広島大学教育学部教育学科卒業、同大学院教育学研究科単位取得退学、1983年より新潟大学教育学部附属教育実践研究指導センター、1991年より2021年3月まで広島大学。2015年から4年間は附属小学校長を併任。2021年4月より安田女子大学・児童教育学科に着任。2025年4月より幼児教育学科に異動。
教育学、教育方法学、ドイツ教授学、学習集団研究、授業研究
教育方法学は、教育の「方法」つまり「どのように(how to)」をテーマに、どのように教育を「すべきなのか」という教育の思想や理想に関する理論的側面と、どのように教育を「しているのか」という教育の現実や実態に関する実践的側面との、二つの側面からアプローチします。理論と実践は相互に影響し合いながらも、ときに背反し矛盾します。この理論と実践の関係を「問い続ける」ことが、教育方法学研究の原動力になっています。と同時に、この理論と実践の関係を「学び続ける」ことが、これからの教員や保育士には求められています。

広島大学学校教育学部卒業、広島大学大学院博士課程後期修了。博士(教育学)。岡山市内の短期大学教員を経て、2009年4月安田女子大学に着任。青年期および成人期における他者とのかかわりの中での自己の発達研究の成果を生かし、現在は、教員および保育者の養成に従事している。
「発達心理学」「教育相談の理論と方法」「幼児理解の理論と方法」を担当
子どもの教育、保育に携わる上では、人間の成長、発達のプロセス、メカニズムについて理解することが重要です。心理学では、乳幼児期から成人期に至る生涯発達の流れや、人間の発達のさまざまな側面についての基礎的概念の理解を深めます。これらを基礎に、さらに子ども理解のあり方や、子どもの発達援助のあり方について追及していきます。近年では、子どもを育てている親を支える、つまり子育て支援の重要性がいわれています。心理学では、子どものみならず、親世代として成人期の心理も取り上げます。子育てする親についての理解を深め、適切な子育て支援のあり方について考えることができる教員、保育者の養成に努めています。

日本体育大学卒業。広島大学大学院総合科学研究科人間科学部門身体運動科学領域博士課程修了(学術博士)。学生時代から主に高校生や小学生を対象にバスケットボールを指導し、現在は大学生の指導を行なっている。前職の安田小学校では長年体育専科として子どもの体力作りに取り組み、教頭を経て現職に至る。
身体教育学、スポーツ科学、応用健康科学、子ども学
「健康」、「運動遊びの基礎」、「からだの科学」、「健康スポーツ」など健康や体育に関する科目を担当しています。現場での経験を生かし、子どもの体力や自己効力感に関する研究も行なっています。生きていく上で、健康は子どもにとっても大人にとっても一番重要であることは言うまでもありません。保育者として健康な子どもをどのように育てていくか、家庭への支援はどうあるべきかなど講義や実践を通して学んでいきます。

佐賀大学教育学部小学校教員養成課程卒業、広島大学大学院博士課程前期幼児学専攻修了、広島大学大学院博士課程後期教育学専攻満期退学。幼稚園、小、中、高等学校までの教員免許を取得。子どもの育ちを繋げる保幼小の連携を研究。発達障がい児のサポートとして県内の保育所・幼稚園への保育アドバイザーを担当。
幼児教育学・保育者養成論
幼児教育学は、子どもの育ち、幼児教育・保育に関する法規・歴史・思想・制度、保育内容、保護者支援など多岐にわたる学問です。更に、理論を学んでも、実際の子どもたちの前で、実践できなくては習得できたとは言えない学問でもあります。0歳から6歳までの乳幼児を対象としていますので、難しい顔をして、難しい内容を語るのではなく、乳幼児の気持ちに寄り添って、笑顔で分かりやすい言葉や、表情で保育することが求められます。授業も具体例を紹介しながら、初めて幼児教育学を学ぶ方が楽しく積極的に学べることを心がけています。

広島大学学校教育学部卒業、同大学大学院教育学研究科修士課程幼児学専攻修了、同大学大学院教育学研究科博士課程後期幼児学専攻単位取得退学。徳島県と広島県の短期大学で保育士・幼稚園教諭の保育者養成に約30年間携わった後、2025年4月より現職。「幼児と言葉」等の科目を担当している。
保育学、教育社会学、教育人類学、多文化教育
昼寝などの睡眠時の乳幼児の安全・見守りや送り迎え時の保護者対応、絵本の読み語り等の業務に人に代わるセンサーが導入された場合、そこで働く専門性の意味合いや養成、ならびに、研修内容に大きな影響を及ぼすと考えられます。2008年から毎年、保育者養成に「芸術における学習」を導入する試みとして、演劇ワークショップの開催と受講生による劇の上演を敢行し、保育界に少しばかりの還元をしてきました。等価交換でも、人間万能でもない、新たな言葉の領域を専門分野の異なるアーティストの協力を得ながら研究しています。

川崎医療福祉大学医療福祉学部卒業。佛教大学大学院社会学研究科社会福祉学専攻、同志社大学大学院総合政策科学研究科大学院修了。修士(社会学、政策科学)。社会福祉士、精神保健福祉士、保育士。社会福祉協議会、精神障害者社会復帰施設などでソーシャルワーカーとして勤務後、大学・短大で保育士養成教育に携わる。
児童家庭福祉、精神保健福祉、専門職養成教育
児童家庭福祉、障害児保育、社会的養護など科目を担当し、子どもの権利や生活を守るための法律や制度・福祉施設に関することや障害児の保育、虐待を受けた子どものケアなどについて授業をしています。また、精神疾患のある保護者による子育てやヤングケアラーなどの課題について関心をもち、そのような課題を抱えて生活する子どもらが安心して、そして自分らしく生きていけるための支援のあり方について探求しています。

京都大学教育学部卒業、九州大学大学院人間環境学府修士課程修了、同博士後期課程単位取得後退学。博士(心理学)。南九州大学人間発達学部専任講師、同准教授、安田女子大学教育学部児童教育学科准教授を経て、2025年4月より現職。群馬県前橋市出身。
教育心理学、発達心理学、教育工学
教師や保育士として働くためには、子ども達の「心や身体の発達の仕方」や、「発達過程に応じた認知の仕方」について学びながら、「適切な教育方法や保育方法」を理解することが欠かせません。社会の変化に応じて子ども達に育みたい資質・能力が変わったとしても、人間が何かを学習する過程で起こること、必要なことは大きく変わりません。教授・学習活動に関わる問いの探求を通して、人間が「学ぶ」「育つ」こととは何か、その過程を支援するために教師や保育士が出来ること(「教える」「関わる」「支援する」等)は何かを体系化するのが、教育心理学です。

奈良女子大学大学院人間文化研究科社会生活環境学専攻。博士(社会科学)。福祉社会学の視点から少子化を研究。 熊本県庁で、児童相談所や福祉事務所、市町村の児童福祉主管課など現場の実践をはじめ、エンゼルプランの策定や少子化対策の企画立案実践、介護保険事業計画等を担当。2021年4月、安田女子大学に着任。
社会学、社会福祉、少子化、行政とAI・DX、ライフデザイン
社会福祉や子ども家庭福祉、子育て支援、ライフデザインなどの科目を担当しています。 AIの急速な発展によって、私たちの社会は大きな変革を迫られています。いずれAIに代替されてしまう仕事も多くなることが予想されています。しかし、保育者のように、人が人の成長を見守り支援する仕事は、人でなくては出来ません。今後も、保育者は、子どもたちの成長を支援するとても重要な役割を担い続けるでしょう。現在の保育現場の課題は、保育者が本来の保育以外の仕事に追われていることです。そのため、AIを保育者のパートナーとして、人でなくても出来る仕事を、AIに役割分担をしてもらう必要があります。保育者が本来の保育の仕事に専念し、保育の専門性を高めることができるようなAIの活用方法を探究していきます。

国立音楽大学音楽学部音楽教育学科卒業。山梨大学大学院教育学研究科修士課程修了。昭和音楽大学伴奏研究員、帝京学園短期大学、藤女子大学を経て現職。専門は芸術実践論、音楽教育学。特にピアノ伴奏法に関して学術的・実践的な研究を行っている。
芸術実践論(ピアノ伴奏法)、音楽教育学(保育者養成における音楽教育)
芸術実践論として、ピアノ伴奏法に関する研究を軸としています。ピアノ伴奏というと合唱などで必要となり、ちょっとピアノが弾ける人が担当する、というようなイメージを持っているかもしれませんが、歌や楽器の伴奏をするときには、いわゆるソロピアニストの能力とは違った能力が必要となる場合があります。その能力はどのようなものであり、それを身に付けるためにはどのような練習が効果的なのか、といった伴奏ピアニスト特有の技術や能力に関しての研究を行い、教育・保育者養成における器楽指導に応用することを目指しています。

東京大学卒業。東京大学大学院修士課程および博士後期課程修了。音楽教育史の分野で博士(教育学)を取得。東京大学教育学研究員、埼玉県内の私立中学校・高等学校教員、東京経営短期大学専任講師を経て、2018年4月より安田女子大学に赴任。
音楽教育の歴史~現代における応用可能性を探究する~
音楽教育学は、演奏力と教育法の大きな二つの柱から成り立っています。単に高い演奏力を追い求めるだけでは、保育者や教員の仕事は務まりません。音楽の楽しさや奥深さを子どもにいかに伝えるか、その指導方法を追究することなしに、音楽教育は成り立たないのです。具体的には、模倣・繰り返し・イメージ化などの活動が音楽教育に及ぼす影響について、その基礎にある歴史的な音楽教育家たちの思想をもとに、考究することを目指しています。また、それらの歴史的な教育家たちの有した知識を、現代の音楽教育や保育に活かすための方策を探究しています。

広島大学教育学部卒業、広島大学大学院博士課程前期/後期修了。博士(教育学)。幼少期からバトントワリングを習い、大学からはダンスを専門的に学ぶ。有名アーティストの現地バックダンサーやコンテンポラリーダンサーとしての舞台経験もある。2017年4月より安田女子短期大学保育科に着任し、2025年4月より安田女子大学幼児教育学科に着任。
身体教育学、幼児身体表現、体育科教育学
身体表現、保育内容表現に関連する講義を担当しています。一般的に身体表現(ダンス)の「よい動き」について言語化をすることは難しいですが、「時間」「空間」「力」の視点から身体表現(ダンス)に共通する「よい動き」とは何か研究しています。また、小学校以降から身体表現(ダンス)は体育として位置づけられています。その中で「自分は運動が得意でないからできなくても仕方がない」というような体育授業への≪劣等コンプレックス≫が高い子どもに対して、少しでもそのコンプレックスを低減させて体育授業が好きになるような授業内容・方法および教授方法について研究しています。