



コロナ禍に読む『株式投資のための財務分析入門』髙田 裕講師(著)
2020.08.07
2020年6月に出版された『株式投資のための財務分析入門』、著者は現代ビジネス学科の髙田裕講師です。
先生は元外資系金融機関においてファンドマネージャー、株式アナリストとして企業調査・運用業務に従事された経歴の持ち主。本書は先生による前作『外資系アナリストが本当に使っているファンダメンタル分析の手法と実例』の入門編にあたる位置づけとのこと。
どういった方に本書を手にしていただきたいか、また現状のコロナ禍における企業の財務分析のポイントなど、先生にインタビューを行いました。

私の専門は、「ファイナンス」や「金融経済学」といわれる領域です。これまで、「金融機関のリスク管理」や「株式市場の株価変動要因」などの研究を行ってきました。加えて、私は金融機関やシンクタンクで、経済予測・市場分析・企業調査の実務家として、実際に多くの企業を見てきた経験があります。そのため、実務感覚から生まれた素朴な疑問を大切にしながら、実務と理論のバランスのとれた研究を目指しています。
本書と兄弟本にあたる前作『外資系アナリストが本当に使っているファンダメンタル分析の手法と実例』に共通するのですが、ファイナンス理論を踏まえた本格的な実践書を出版したいと考えたからです。株式投資に関する書籍は多くありますが、「理論なき実践」に陥っている書籍か、「学術書」のどちらかに偏っていると感じていました。「理論なき実践」は砂上の楼閣に過ぎず、「学術書」は実務家にとっては時に実践的ではありません。もちろん時代に左右されず、本質的な議論をするには学術的な理論を踏まえる必要があります。そのため、実務に必要な理論を取捨選択しながら、段階を踏んで丁寧に解説することで、実務にも対応できる実践書としました。このような書籍の必要性について、出版社と意見が一致したことが執筆の背景です。また、本書『株式投資のための財務分析入門』については、前作で紙面の関係から解説しきれなかった財務分析に焦点をあてました。
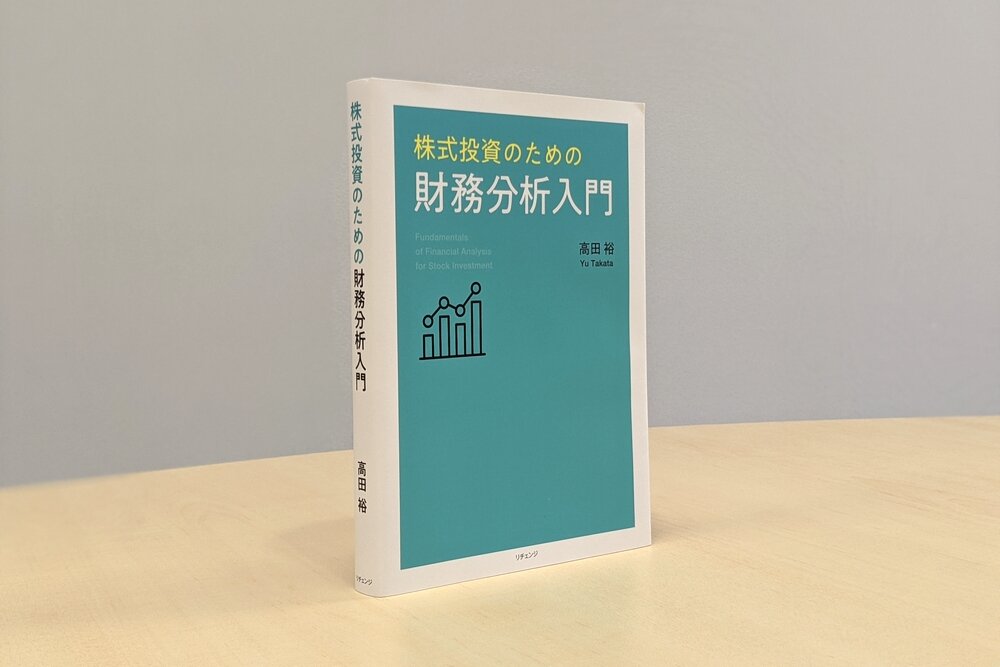
コロナ禍の影響を受けて、不幸なことに世界中の経済活動が止まりました。企業業績の悪化は避けられません。長期的な停滞を回避するため、危機をどう乗り越えていくかを考えるべきです。本書の5章で説明したのですが、「中長期的に良好な事業」であったとしても、企業は資金繰りなどの一時的な危機から倒産に追い込まれる場合があります。倒産を回避するため、社会全体でスピーディな支援が必要ということです。平常時の理屈を捨て、社会全体が早期に一丸となるべきです。
一方で、企業は社会潮流(社会構造の変化)に対応して、常に社会に必要な存在へ変革し続ける宿命があります。コロナ禍を受けた社会変化に対応し、自らの努力で変わらなくてはいけません。その努力が、長期的な成長の原動力となります。株式市場を含む資本市場は、この企業の不断の努力を長期的視点から応援していく場とならなくてはならないでしょう。

書籍内に記載した対象読者ではないものの、私が読んでほしい「隠れた対象読者」がいます。「金融機関の若手社員」です。金融機関に入社すると目先の業務(ノルマ)や社内政治に追われ、金融マンとしての原点を見失ってしまうことがあると感じています。私が考える原点とは、「企業の夢や理念を共有し、長期的な観点から社会に必要な企業を応援する」という気持ちです。その気持ちを大切にしながら、どうやって企業分析・投資を実践するのか、心がけて執筆しました。実は、若手金融マンだった頃の悩んでいた私が読みたかった書籍となっています。
コロナ禍により、慣れないオンライン授業や課外活動の制限など、学生生活に多大なる影響がでていることを率直に残念に思っています。大学時代に様々なことに挑戦し、たくさんの失敗を通して学んでいく経験は、人生の貴重な宝物です。社会で活躍するための原動力となります。そのため、コロナ禍の制約は本当に悲しいです。しかし、人生においては時に直面した環境を受け入れなくてはなりません。どのような条件だとしても受け入れて努力することが重要です。今は、たくさんの書籍を読んで、自分の関心がある領域を深堀りしていきましょう。「挑戦する機会が必ず来る」と信じ、先人たちの知恵を踏まえて、自分の好奇心と真剣に向き合うということです。迷った時は、私たち教員に大いに頼ってください。精一杯、皆さんの好奇心を応援していきます。

【略歴】
同志社大学経済学部卒業。大阪大学経済学研究科修士課程修了後、広島銀行に入行。コムジェスト・アセットマネジメント、三井住友トラスト基礎研究所などで調査・研究業務に従事。その間に一橋大学国際企業戦略研究科(金融戦略・経営財務MBA)を修了。現在は、ファイナンスの分野で主に実証研究に取り組んでいる。