




大阪市立大学大学院工学研究科都市系専攻修了。工学博士。一級建築士。APEC建築家。インテリアプランナー。インテリアコーディネーター。日本建築士事務所協会連合会奨励賞、日本建築学会作品選、デザインフォーラム、インター・イントラスペースデザインセレクションなど受賞。
建築計画・都市計画・建築設計
「建築空間をプログラムする」
建築における計画とはProblem Seeking(問題を発見すること)です。人間生活と建築空間の関係という視点から、生活の基本的空間である住居の問題や各種建築における計画上の問題を分析し、これからの建築空間をプログラムします。また、設計では唯一無比の正解というものはありません。深い洞察と創造力からプログラムされた新しい空間を提案し、具体的に形にできるのが、いちばんの魅力です。
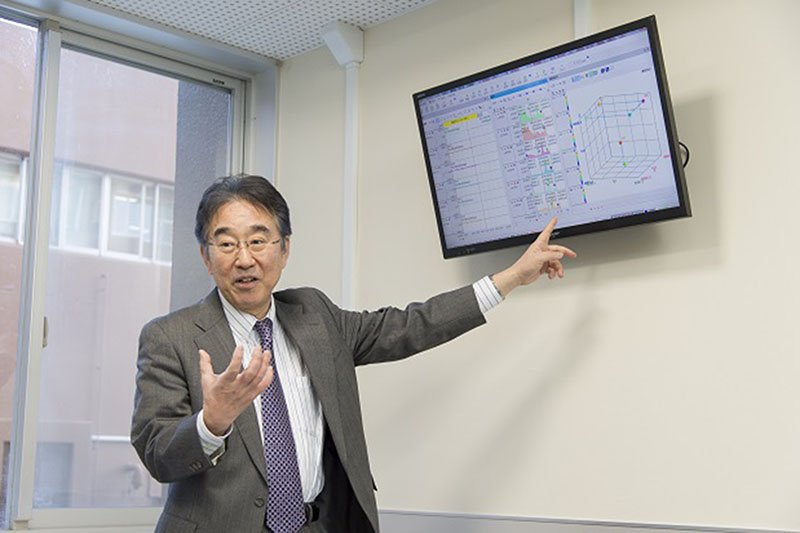
九州大学工学部建築学科卒業後、同大学院工学研究科博士後期課程を修了し、九州大学工学部助手・助教授を務めた後、建設省(現国土交通省)建築研究所に出向。さらに広島大学大学院教授を経て現職。建築材料・生産学が専門で、建築物の長寿命化のための材料評価や検査・診断技術の高度化のための研究に取り組んでいる。日本建築学会学会賞(論文)、日本建築仕上学会賞(論文賞)、日本コンクリート工学会功労賞、セメント協会 論文賞、日本建築積算協会会長表彰、国土交通大臣表彰などを受賞。工学博士。
建築材料学・建築生産・建築物の予防保全
「建築物を長持ちさせるための研究・技術開発」
建築物には、機能性、快適性そして安全性などの多くの性能・品質が要求されます。近年、経済成長の伸び悩みや少子高齢社会の到来を受けて、建築物の「長寿命化」が建築物に要求される品質として非常に重要な位置を占めるようになってきました。このような時流を受けて、私は新築段階の「耐久設計」と維持管理段階の「検査・診断技術」の観点から、建築物の長寿命化のための研究を行っています。健全な建築物を生産し、重大な不具合が生じる前に適切に手を打って長持ちさせようとする考えは、人間の健康管理と全く同じです。私は建築物の耐久設計や維持管理段階の健康診断の手段として、他の理工学分野の技術者と共同で開発した各種センサを活用し、長寿命化のための建築部材設計や維持管理手法の高度化のための実験研究に取り組んでいます。

(有)アーキスタジオ川口一級建築士事務所 代表取締役。建築家、長岡造形大学教授(2009〜2022)。新潟県生まれ。東畑建築事務所、アトリエ・ホライン(ウイーン)勤務をへて'89年アーキスタジオ・オゾン設立。'93年アーキスタジオ川口に改称。建築からプロダクトまで多彩に活躍。2011年グッドデザイン賞受賞(桐着物チェスト)。2014年グッドデザイン賞受賞(CH14レジリエンス住宅)。2015年「第32回住まいのリフォームコンクール」住宅リフォーム推進協議会会長賞受賞。「大改造!!劇的ビフォーアフター」(テレビ朝日)に8回登場。代表作:蔵王のもりこども園/新潟県長岡市2019(http://archi-kawaguchi.com)
建築・インテリア他デザイン全般
1998年から「デザイナーのための内外装材チェックリスト(彰国社刊)」の執筆のため建築材料や構法への造詣を深め、地球環境問題に関心を持ちサステナブルデザインやユニバーサルデザインに関する独自の研究を重ねてきました。サステナブルデザインに関してはLIXIL住宅研究所との共同「レジリエンス住宅CH14 (2013)」の設計(2014年度グットデザイン賞)に繋がりました。ユニバーサルデザインに関しては長岡景観アドバイザー(2011~2022)他の役割に活かし、長岡市等の景観向上に貢献してきました。これら私の<地球環境〜景観>を視野に入れた<素材〜建築>の横断的なデザインは幅広い評価を受けかつ独創性の高いものでもあります(TV「大改造!!劇的ビフォーアフター」8回出演)。また「スクラップ&ビルド」の日本の建設業界を「ストック活用」の方向に誘導してきたと思います。これらの実績を活かし、ポスト・コロナの時代のデザインへと展開していきたいと考えています。

早稲田大学理工学部建築学科卒業。住宅メーカー勤務の後に筑波大学大学院人間総合科学研究科にて博士(デザイン学)を取得。森林総合研究所研究員、島根大学准教授を経て現職に。伝統的な住まいや集落について暮らしの視点から分析し、古民家等の利活用と地域活性化に向けた取り組みを行っている。
民家史、建築史、木造建築構法、伝統的集落、古民家活用、地域活性化
中国地方を中心とした伝統的な建築と街並みを残す地域を対象として、集落構成と建築構法に関する調査研究を行っています。建築物の間取りや構造・内装などを記録したうえで、地域の歴史や建物の利用法について確認し、建築物等の成立要因に関する分析を行います。また、地域の伝統産業に着目した作業空間に関する研究、生業に対応した付属小屋に関する研究、石材を利用した石造建築物に関する研究なども継続して行っています。
さらに調査の成果を踏まえ、今後の地域活性化に向けた実践的な取り組みを行っています。各地で実施されているまちづくりに関する調査に加えて、実際の古民家を対象とした改修作業等を実施し、公的機関や地元住民と連携しながら今後の地域の在り方について検討しています。

京都府立大学大学院人間環境科学研究科生活環境科学専攻博士後期課程修了。博士(学術)。国立高専において22年間にわたり技術者教育に従事し、PBL(課題解決型学習)やキャリア教育の多数のプロジェクトを推進。その後、福山大学工学部を経て現職。専門は住環境や建築計画。高齢者住宅や発達障害のある子どもの学習環境など、多様な人々が共存できるインクルーシブな住環境の研究に取り組んでいる。
建築計画・住宅計画・福祉住環境
すべてのこどもが安心して学べる環境づくりには、空間のデザインが重要です。しかし、単に「良さそうだから」ではなく、科学的な根拠(エビデンス)に基づいたデザインが求められます。特に、発達障害のあるこどもたちは、音や光の刺激に敏感だったり、集中しやすい環境が必要だったりと、それぞれに合った学習空間が必要です。そのために調査を通じて課題を分析し、データをもとに最適な改善方法を提案する研究を行っています。 例えば、国内外の学校で学習環境の実態を調査し、生徒や先生へのヒアリングや空間の実測を行い、どんな環境が学びやすさにつながるのかをデータとして記録します。その結果をもとに、照明や色彩、家具の配置、音のコントロールなど、より良い学習環境を実現するための方法を検討します。こうした研究によって、発達障害のあるこどもだけでなく、すべてのこどもにとって快適で学びやすい環境づくりにつながると考えています。
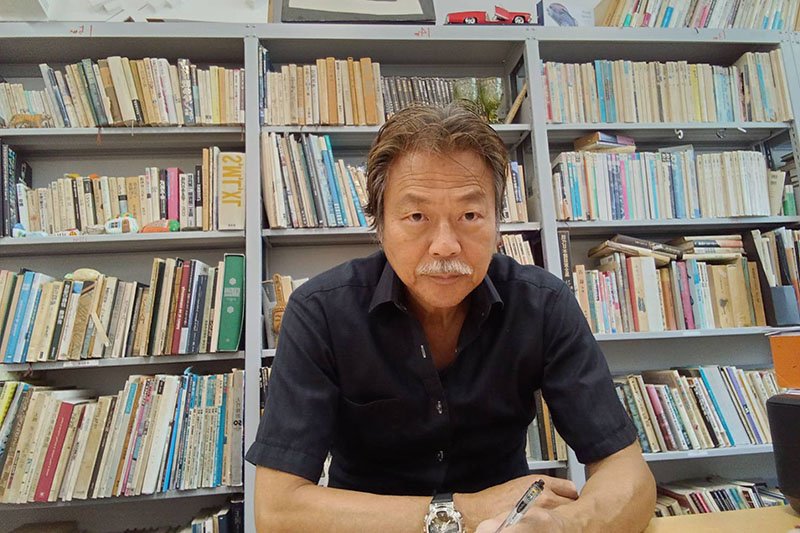
京都大学工学部建築学科卒業後、大成建設設計本部勤務。
大成建設退社後 「前田紀貞アトリエ一級建築士事務所」、そして設計活動と同時に建築創作を深めてゆく為の「前田紀貞建築塾」を主宰。大学での教育活動・研究活動と同時に、建築を志す人たちを対象に、建築塾・勉強会・ワークショップなど、未来に建築を志す後進たちの育成を行っている。これまでの作品
建築デザイン、建築論、まちづくり
建築というものは、機能や構造や環境について構想することから作られるものですが、それと同時に、いやもしかしたらそれ以上に一考されなければならない事柄があります。
「 住まう とはなにか?」という至極当たり前のことを真正面から問い直してみることがそれにあたります。そんなことのために、私は幾つもの具体的試みをしています。
例えば、住まい手の「脳波」から建築を構想してみること、「波の音」を建築にしてみること、「森の木々の立ち方」から部屋割りを決定してみること、サイコロを投げて出た目で建築を創作してみること、等です。
これらいずれもが、普通に考えられている建築の方法とは違うように思うかもしれませんが、実はこうした試みのなかにこそ、本当の意味での「住まうこと」への希求が潜んでいるのです。
建築は工学的であると同時に、文学的であり芸術的でもあります。その両極の隔たりを感じながら同時にそこにある同質性を思い描いてみること、そこにこそ、建築の楽しみと醍醐味があるのです。

宇都宮大学工学部建築工学科卒業。宇都宮大学大学院工学研究科建築学専攻修了。早稲田大学にて博士(工学)を取得後、積水ハウス株式会社、松江工業高等専門学校教授、長崎総合科学大学教授、国立保健医療科学院統括研究官などを経て現職に。企業在職中にシックハウス問題に取り組み、現在は新型コロナ感染症対策のための空気浄化技術やアレルギー対策技術についての研究に取り組んでいる。
建築環境工学、建築設備学
空気の汚染が気づきにくい問題であるように、室内環境に関する研究分野は、住まい手にとって、環境の良し悪しが分かりにくく、問題を生じさせやすい分野といえます。新型コロナ感染症もその一例です。このため、室内環境が「今現在どのような状態か?」を正確に把握し、適切な対策を講じることが求められています。この問題の対策には、換気や空気清浄が有効な技術とされているため、換気設備が不十分な実際の保育施設に対して、機械換気の改修を行い、その効果検証を実施しています。また、住宅の高断熱・高気密化が進む中での昔ながらの生活習慣が湿気やカビ・ダニなどの問題を引き起こす可能性があるため、それらへの対策も検討しています。これらの研究を通じて、室内環境の改善に貢献したいと考えています。

東京都出身。芝浦工業大学大学院工学研究科地域環境システム専攻(博士後期課程)単位取得満期退学。博士(工学)。一級建築士。アトリエ・天工人に勤務後SIT総合研究所ゼロエネルギー建築研究センター、サステナブル居住工学センターに所属。設計の経験を生かして、室内環境が健康や美容、アンチエイジングに及ぼす影響に関する研究に取り組む。アーキテクチャー・ラボに参画。
建築環境、室内環境、住環境
【アンチエイジングからみた室内環境による皮膚と睡眠への影響】
現代において「見た目」をテーマとした医学的アプローチが注目されています。建築領域では、睡眠が室内環境で加齢現象を考える上での重要な要因と考えられています。また「見た目年齢」に影響を与える環境要因としては、室内の乾燥や気流があります。これまで睡眠に最適な室内環境と空調制御についての実験を行ってきました。実住宅においては睡眠中にパーソナル加湿機を使用し、顔周りのみに加湿をした場合の睡眠の質への影響と皮膚について解析をしました。結果、冬の睡眠時の加湿は入眠を早めました。入眠が早くなることで睡眠の質が上がります。さらに夏冬ともに加湿を行ったことで皮膚のキメも整い皮膚水分率も上昇しました。このように室内環境をコントロールすることは非常に重要です。

台湾出身。京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻博士課程修了。博士(工学)。日本学術振興会特別研究員(DC2)・外国人特別研究員(PD)、朝陽科技大学助教授、中原大学助教授、京都光華女子大学短期大学部講師を経て現職。住生活学、住居学、インテリアデザイン分野の科目を担当しており、日本植民地建築の研究、保全活動、まちづくりや伝統産業との地域連携にも取り組んでいる。都市住宅学会博士論文最優秀論文賞、住総研研究選奨、日本建築学会奨励賞などを受賞。
住宅計画、住生活学、住居史、居住文化、インテリアデザイン、植民地建築、まちづくり
主に日本植民地であった地域において昭和戦前期に日本人が海外で開拓した居住地、日式住宅の建設経緯、住宅・建築計画を解明するとともに、日本人の海外での住様式、住生活の実態に関する研究に取り組んでいます。フィールド調査を通して、居住地の開拓史、住居史、居住文化の長きにわたる相互影響を描き出すことができ、地域の歴史的・文化的価値を再発見することに繋がっています。また、歴史的な住宅建築、まち、地域を対象とし、まちづくりや地域連携により伝統産業の技術や知識を活用して既存材料を利活用するものづくりの教育と研究、住環境に適応するインテリアの建材の研究開発も行っています。
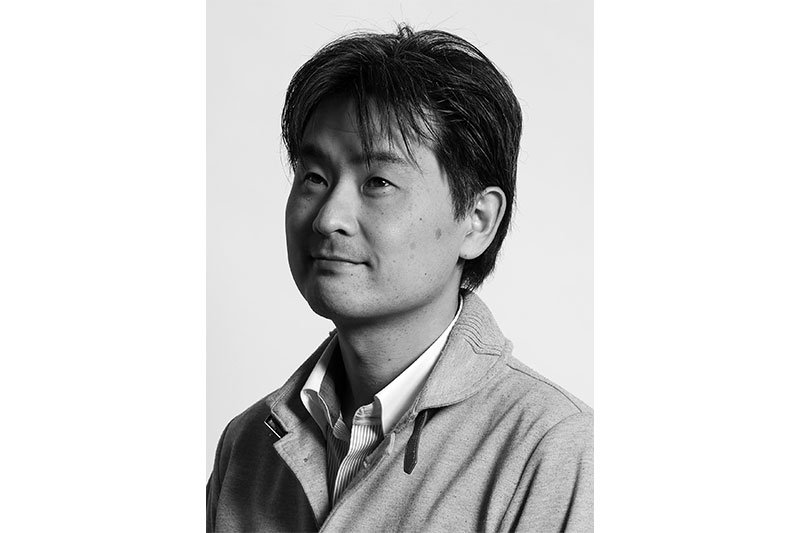
株式会社一条工務店にて住宅の研究開発に携わり、全館床暖房を開発。株式会社住宅みちしるべ一級建築士事務所を設立し、代表取締役を務める。多数の戸建て住宅設計を手掛け、省エネ設計やパッシブ設計を得意とする。多数のメディア出演やセミナー講演の依頼を受ける。近畿大学建築学部非常勤講師として10年以上にわたり、住宅設計や設備、施工、建築環境に関する講義・演習を担当。エネマネハウス2017では近畿大学チームの設備WG統括として参加し、優秀賞、エネルギー健闘賞、People Choice Award受賞に貢献。研究者として寝室の睡眠環境についての研究を続ける。機械学習やAIを利用した分析を主とし、体に健康的な寝室環境の解明に挑んでいる。
建築環境工学、建築設備、住宅設計、パッシブ設計、省エネルギー設計、高断熱設計
実際に自身が設計に携わった高断熱住宅を対象とし、床下エアコンの省エネルギー性能に関する調査、分析、シミュレーションを行う。床下エアコンとはエアコンの送風先を床下とすることで足元を暖める手段である。一台の一般的なエアコンによって、住宅の全体を暖房する手法であり、エアコンの最適な運転方法や、送風方法、断熱方法についての研究を行っている。また、近年の高断熱化に伴う高湿化への対処として夏の床下エアコン利用方法についても研究を行う。 睡眠中の平均心拍数を分析対象として、快適な睡眠環境の研究を行っている。寝室環境は地域によって大きく異なり、比較的温暖な大阪、冬の寒さが厳しい山形、蒸暑地域と呼ばれるタイや沖縄において調査を行う。睡眠中の温度環境や二酸化炭素濃度、音や照度環境、寝具や着衣の状態それぞれの影響について評価を行う。睡眠マネジメント研究センターのある山形大学や近畿大学と共同で研究を行っている。

早稲田大学理工学部建築学科卒業。建築家の安藤忠雄氏、古谷誠章氏の設計事務所に勤務しながら建築設計の実務を学ぶ。その後、広島県で自身の設計事務所を主宰し、瀬戸内の豊かな場所性を取り入れたコンクリート打放しのシンプルな現代住宅の設計を手掛ける。この間、非常勤講師として複数の大学で建築設計教育にも携わってきた。一級建築士。
建築意匠設計、建築空間学
私の研究は、建築意匠設計における「設計手法と空間論」の実践的な探求です。建築の抽象的な空間構成に注目し、具体的な生活や周辺環境との関係を深める方法を考察しています。シンプルでありながら豊かな空間を創り出すため、複雑な設計条件に秩序を与えるアプローチを模索しています。
また、構造や環境、歴史、場所性の研究を融合させ、プロジェクトごとに異なる地方の特性を活かした豊かな建築の可能性を探ります。さらに、デジタル技術と職人の手仕事を組み合わせた、新しい建築のあり方も追求しています。
これらの研究を通じて、普遍的でありながら革新的な設計手法を確立し、地域の特性を活かしつつ、それを世界へと広げることを目指しています。

広島県出身。早稲田大学・大学院修士課程修了、早稲田大学大学院博士課程単位取得退学。主な業績に、ユネスコ世界遺産アンコール遺跡バイヨン寺院の保存修復、旧本庄商業銀行煉瓦倉庫の再生(ユネスコアジア環太平洋文化遺産保全賞、日本建築学会作品選奨)、閖上港朝市を中心とした震災復興(科学技術分野の文部科学大臣表彰・科学技術賞、日本建築学会賞、グッドデザイン特別賞)など。形態と素材から導く構造デザインや歴史的建造物の保存再生を専門とする。
構造デザイン・歴史的建造物の保存再生
"未知の解明と先端技術"
歴史的建造物の保存再生や構造デザインなどを主な研究のフィールドとしています。なかでも、学生時代からカンボジアのユネスコ世界遺産アンコール遺跡で研究を行っています。12世紀頃の建設から800年近くを経て存在している建造物には、未だ未解明の技術や設計思想があり、最先端の技術開発なども行いながら、国際協力の一環として様々な専門家が協同して研究や修復が行われています。そうした研究成果や知見は、国内の歴史的建造物の保存再生などにも活かされていて、これからの社会で求められる建物の保存再生などにも活かされると思います。3DCGや人工知能(AI)などの新しい技術も研究に取り入れながら、楽しんで研究を行っています。
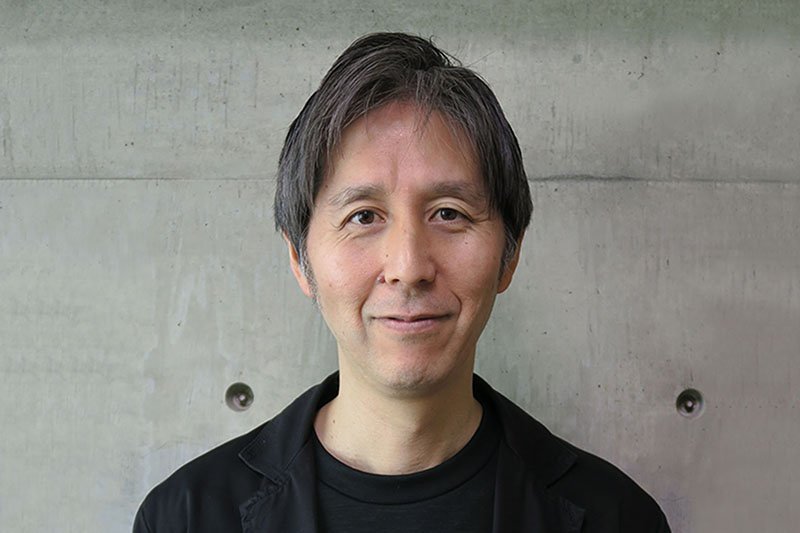
早稲田大学大学院理工学研究科建築学専攻修了、南カリフォルニア建築大学大学院(Southern California Institute of Architecture)修士課程修了、早稲田大学大学院創造理工学研究科建築学専攻博士後期課程を経て、博士(工学)。一級建築士。山下設計、コープヒンメルブラウ(CoopHimmelblau)、メタボルテックスアーキテクツにて建築設計などに従事。日本大学生産工学部、長岡造形大学造形学部非常勤講師を経て現職。
建築計画・都市計画
世界的には環境問題をきっかけに、持続可能な都市づくりを目指し、コンパクトシティや15分都市構想などが進められるなかで、都市における良質なアフォーダブル(低廉な)住宅の拡充が課題となっています。先進的な試みを行うアメリカなどにおけるアフォーダビリティ問題は、所得格差や都市労働者居住の問題だけでなく、多様で魅力的なまちづくりやパッシブ・デザイン、デジタル・デザインなどの課題も包含しています。
そのため、これまでの米国ミックスト・インカム住宅研究から都市のアフォーダビリティを主要テーマとし、アフォーダビリティが都市にどのような影響を与えるかを研究していきます。そして国内だけでなく海外事例も研究対象とし、それから派生するパッシブ・デザイン、デジタル・デザイン、まちづくり、建築設計の実践などを行い、これからの建築のあり方を模索していきます。
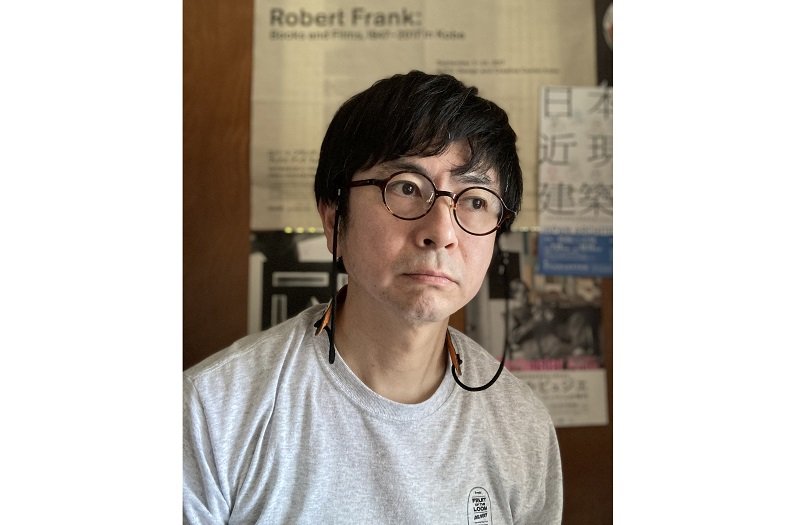
京都工芸繊維大学工芸科学研究科後期博士課程(造形科学専攻)修了。博士課程在学時に京都造形芸術大学(現京都芸術大学)芸術学部(通信教育部)非常勤講師を務める。博士(学術)取得後、京都市立京都工学院高等学校プロジェクト工学科・京都市立伏見工業高等学校工学探求コース兼任助教諭として高等学校の教育に従事。さらに、京都芸術大学芸術学部(通学部・通信教育部)、京都芸術大学大学院芸術研究科(通信教育)、京都美術大学工芸学部、京都市立芸術大学美術学部、摂南大学理工学部、大和大学理工学部など、京阪における複数の大学・大学院で非常勤講師として教育・研究に携わってきた。
西洋建築史、近代建築史、建築論
古来、建築の創作は、建設に先立つ設計の段階で、思い描いた建築を表現する素描や図面、また模型といった媒体の制作を必要としてきました。言い換えれば、建築家をはじめ、建築をつくりだそうとする人は、何らかの表現媒体を介して、自らの頭の中のイメージを具体化しながら、建築を設計してきたといえます。そして、表現媒体をもとに、資金を提供する出資者また工事を行う石工や大工などの第三者に自らの設計(デザイン)を伝え、建築を実現してきたといえるでしょう。つまり、建築設計上の表現媒体なくして建築は生み出されてこなかったといっても過言ではありません。このように建築の創作に欠かせない表現媒体が多角的に議論されはじめたのは、初期近代イタリアの建築理論書においてと考えられています。それを紐解くことで、当時の建築家の設計思想や建築デザインに与えた表現媒体の影響を読み解き、現代にも繋がるかたちで研究しています。それにより、これからの建築や都市のデザインを考える上で学術的に貢献できれば望ましいと思っています。