



宮岸教授が、国立国語研究所共同研究プロジェクトで中国少数民族言語を調査
2024.10.07

日本文学科で日本語教員養成課程授業の教鞭を執る宮岸哲也教授は、フィールドワークでアジアの様々な言語を研究し、国立国語研究所の共同研究プロジェクトに参加して中国少数民族言語を調査しています。
8月13日から29日の日程で、著名な言語学者の柴谷方良先生と国立国語研究所のプラシャント・パルデシ先生とともに、中国の雲南省と湖北省を訪ねました。
雲南省では麗江と大理に滞在し、漢字以外の表意文字として知られる「トンパ文字」を持つナシ語や、宮岸教授が研究を進めているゾゾ語をはじめ、ペー語、リス語、ミャオ語、イ語、チュアン語、プミ語、チベット語といった中国少数民族の言語調査に加わりました。
〈麗江市内トンパ文字案内。ローマ字の下の文字です〉
調査内容は、ものを数えるときに使う「~本」「~枚」「~人」「~匹」のような日本語の助数詞に相当する類別詞が、言語ごとにどのような範囲で、どのように使われるかを調べることです。
日本語では助数詞は数詞にしか付きませんが、言語によっては、指示詞、所有格名詞、形容詞、動詞などにも類別詞が付く場合があります。また、それらが名詞句用法(三本)だけでなく、修飾用法(三本のマツタケ)としても使われるかどうかも調べました。この調査をベースにして本研究のメンバーは、共同して言語全般における類別詞の発展過程を究明し、この現象を論理的に説明しようと研究を進めていきます。
〈大理郊外市場のキノコ売りの女性〉
湖北省ではコロナ禍が収束し、賑わいが戻った武漢にある大学のワークショップに参加し、宮岸教授はClassifiers and Nominalization in Zauzou (ゾゾ語の類別詞と名詞化) というテーマで、英語と中国語を混ぜながら発表してきました。写真は武漢大学文学院のHPに掲載されているものです。
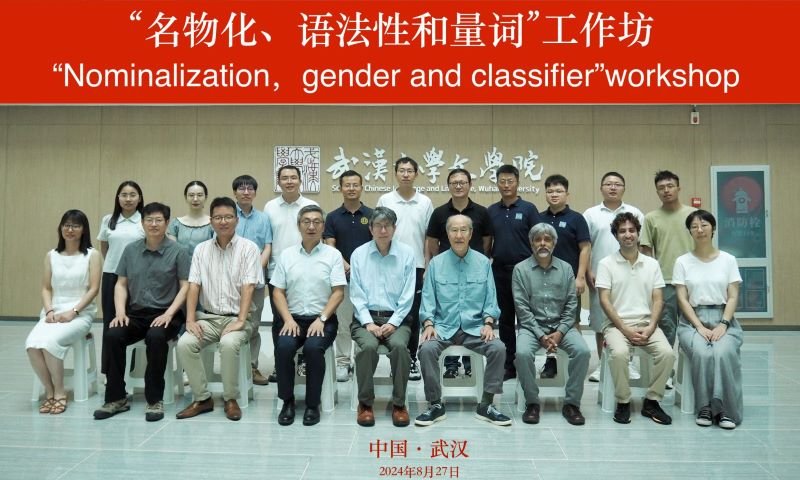
〈武漢大学ワークショップの参加者〉
宮岸哲也先生のコメントを紹介します。
日本文学科2年次後期に開講される「日本語学講読Ⅱ」という授業では、今回の調査で得られたデータを活用し、アジア諸言語のおもしろさや、それらの言語から見つめ直す日本語という内容の充実を図っていきます。
また、トンパ文字の解読にも挑戦していただこうと思っています。