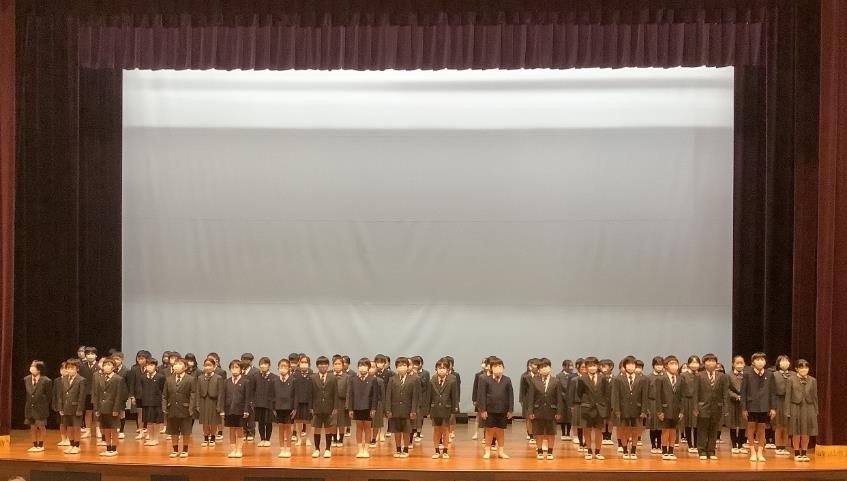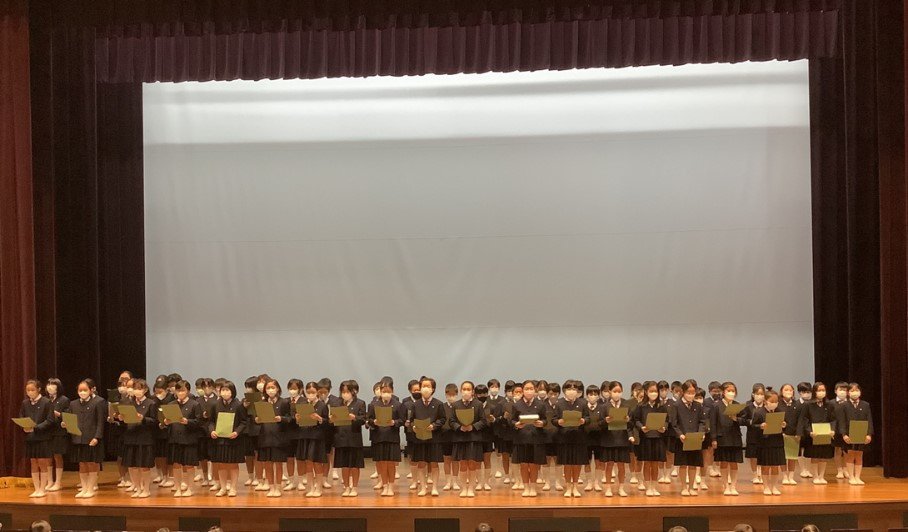くすのきブログ
1年生
宮沢賢治「雨ニモマケズ」
「雨ニモ負ケズ」はひらがなとカタカナが入り混じって書かれています。今年、初めて文字を学んだ1年生にぴったりの作品でした。息継ぎをしっかりして元気に発声できていました。現在、ちょうど宮沢賢治作品をテーマにして描かれた6年生の図画作品が、1階に展示されています。1年生は6年生の作品を目にして、自然に作品への興味関心を深めたのではないでしょうか。作品の持つ前向きなメッセージを胸に、これからの小学校生活も歩んでいってほしいと思います。
2年生
教科書「おばあちゃんに聞いたよ」から、「いろは歌」「十二支」「十二月」
谷川俊太郎「いちがつ にがつ さんがつ・・・・・・・・・」
「いろはうた」はひらがなが一回ずつ使われています。2年生は、もうすっかりひらがなをマスターして、すらすら音読できていました。ことばのかたまりを意識して読んでいたので、非常に聞きやすかったです。谷川さんの詩は、「月」を人に例えているユニークな作品です。作品は、12月を「じ・ゆ・う」と表現しています。2年生の12月、自由自在に音読できるような2年生に成長しつつあります。
3年生
神沢利子 「紙飛行機」 阪田寛夫 「夕日が背中を押してくる」
小泉周二 「朝の歌」
3つの作品にそれぞれ個性があり、それにあわせて工夫をしていることがわかりました。紙飛行機は語り掛けるように音読できていました。夕日が背中を押してくるはリズムよく読み、作品の主題である子どもたちの元気な様子が伝わってきました。朝の歌は梅組と桜組の掛け合いを取り入れて、工夫して音読しました。最後、両クラスの声が重なり、盛り上がっていく表現がうまくできていました。朝の爽やかな空気を感じ、これからも元気に挨拶できそうです。
4年生
社会科「広島県の特産」
広島県の特産物はたくさんあって、大人でも意外と知らないようなものまで、完璧に唱えていました。4年生は、社会科で学んだことを音読で確かな知識にできています。何かを覚えるときに音読してみるのは、定番ですが非常に効果的な学習方法です。そして、クラスで声を合わせることで、楽しくその作業ができたのではないでしょうか。学習内容も高学年に入るにつれ、知識を確実に覚えていくことが求められてきます。4年生のこの時期に、教材内容に加えて、効果的な勉強の仕方も学ぶことができたことは非常に有意義ではないでしょうか。
5年生
松尾芭蕉の奥の細道から序文
有名な歌人である芭蕉は、日本各地を旅して名句を残したそうです。この序文からすでに、芭蕉の旅への思いが感じ取れ、もっと読んでみたくなります。古い作品のため、音読は難しかったと思います。一般的には中学3年生の定番教材ですが、5年生は、高い技術でしっとりと読み上げていました。さすが高学年と言える音読で下級生は感心したのではないでしょうか。事前練習を終えた5年生とたまたますれ違った時、「もっと声を揃えたいのに」と悔しそうにしている児童がいました。真剣に取り組んでいるからこそ生まれてくる気持ちです。高学年として、非常に頼もしく感じました。
6年生
「The World of Storybooks」
6年生は、4つの海外の物語を英語で読んでいました。1人ひとりが担当の物語を堂々と読めていました。もともとはスピーチコンテストの教材で、それらを抜粋したものだそうです。英語の先生が用意したスライドも6年生の発表に花を添え、努力の積み重なりが伝わってくる圧巻の発表でした。6年生は、学習内容も学校内での役割も多く、非常に多忙な学年です。しかし、こうした学校行事で見せる姿は、常に下級生の指針になるものです。安田小学校での6年間の学びの姿を、全校で確認し、今後の目標にできるという点でも、音読集会はとても良い時間になりました。